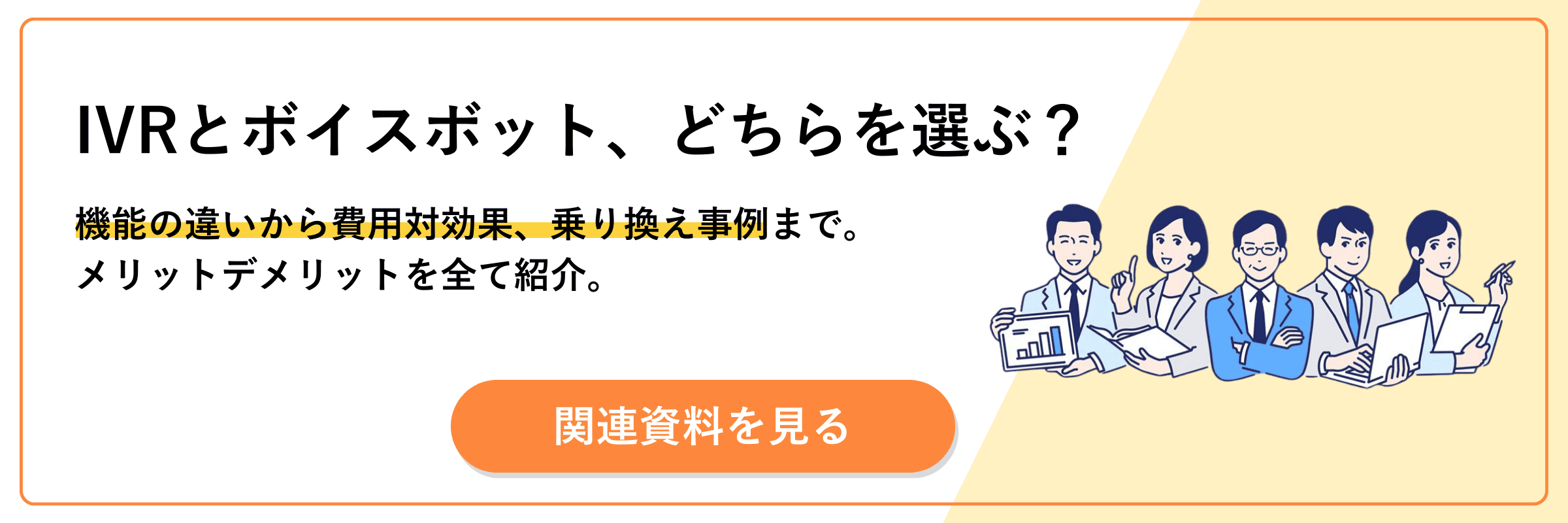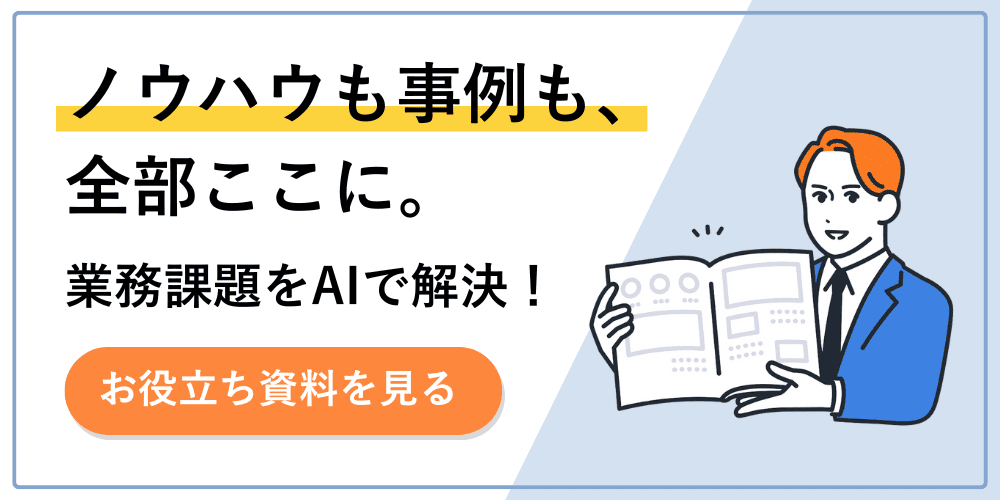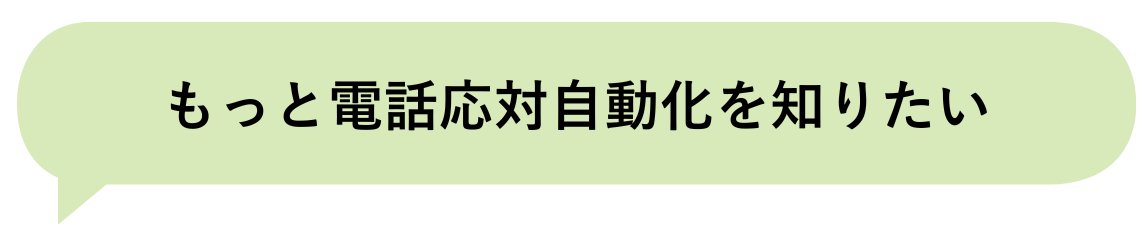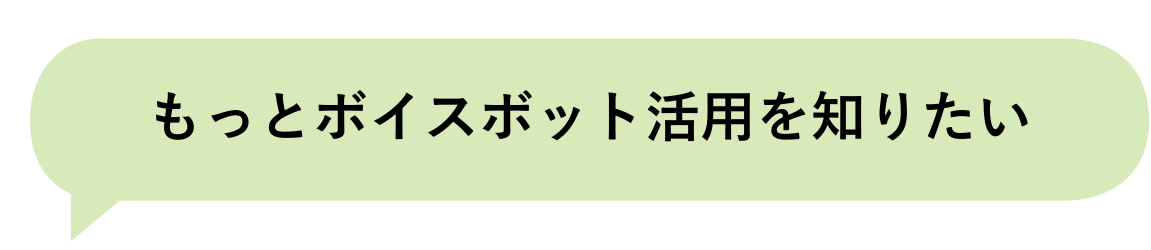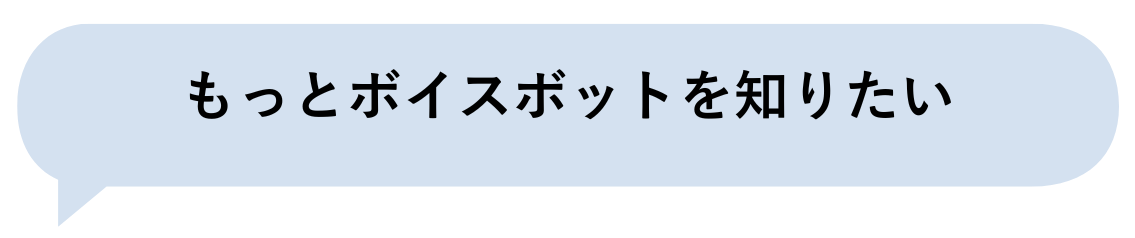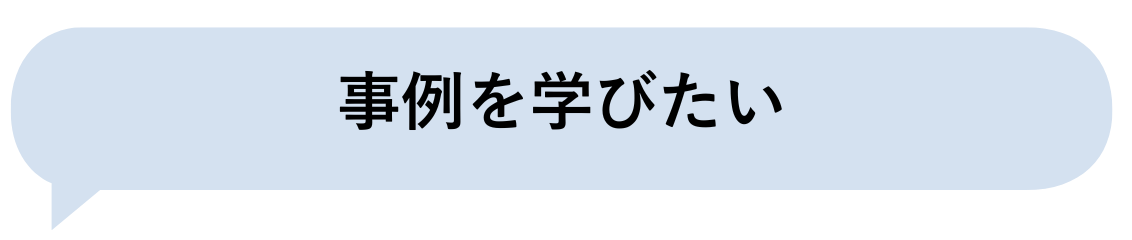オートコールとは架電業務を自動化するシステム!メリットや活用シーンを解説
作成日:2025年10月1日 更新日:2025年10月1日

「オートコールって営業やアンケート調査に使えるの?」
「導入すればどれくらい業務効率化につながる?」
オートコールにより、大量の顧客に一斉にアプローチできるため、営業活動や顧客フォロー、アンケート収集などで活用されています。
人材不足を背景に、電話業務の自動化ニーズが急速に高まっており、自治体や金融機関、教育機関、さらには医療・小売業界まで導入が拡大しています。
この記事を読むことで、オートコールの仕組みやメリットが理解できるだけでなく、自社の業務にどう取り入れれば効率化・コスト削減・顧客満足度の向上につながるのかが分かります。
部署別の活用事例や導入時の注意点も整理しているため、導入判断の参考情報として実践的に役立てていただけます。
オートコールとは?IVRとの関係も解説
オートコールは、営業・カスタマーサポート・マーケティングなど電話を使う多くの部署にあります。人手不足から注目されるオートコールについて解説します。
- オートコールとは
- IVR・チャットボット・ボイスボットとの違い
オートコールとは
オートコールとは、設定されたリストに基づき自動で架電するシステムで、コールセンターだけでなく自治体や教育機関など幅広いシーンなどで活用が進んでいます。電話がつながった後は事前に録音した音声や合成音声を再生する仕組みが一般的です。人が一件ずつ電話をかける必要がないため、大量の架電先に短時間で確実に情報を届けられ、電話業務の効率化による人手不足解消と人件費削減に直結するのが最大の特長です。
代表的な利用シーンは以下の通りです。
- リードへの追客・フォローコール
- 予約確認・リマインド通知
- 督促・期限案内
- キャンペーン効果測定・市場調査
活用シーンは下記で解説しています。
IVR・ボイスボットとの違い
オートコールは基本的に自動発信する機能を指し、IVRやボイスボット、チャットボットは顧客とのやり取りを行う機能を指します。
| ツール名 | コミュニケーション方法 | 利用シーン |
|---|---|---|
|
オートコール |
自動で架電し録音音声や合成音声を再生 |
督促通知、リマインダー、緊急時の一斉連絡 |
|
IVR |
音声ガイダンス後にプッシュ操作で選択 |
部署振り分け、定型的な案内 |
|
ボイスボット |
通話相手の音声を分析し自動応答 |
予約受付、本人確認、FAQ対応 |
自動架電機能を備えた電話業務サポートツール全般をオートコールと呼ぶ場合もあり、商品サービスによってはIVRやボイスボットなどの機能を組み合わせているケースもあります。
IVRやボイスボットについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
IVRとは?電話自動振分けのメリットとコールセンター業務効率化事例
ボイスボットとは?どこまで自動化できる?仕組み・メリット・活用事例を紹介
また、オートコール・IVR・ボイスボットの違いについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
オートコール導入のメリット3選
オートコールには単なる自動発信ツールにとどまらず、以下の3つのメリットがあります。
- 発信業務の効率化
- 業務負荷の軽減
- 一定水準の品質維持
それぞれ紹介していきます。
発信業務の効率化
オートコールを導入するメリットは、大量の発信業務を短時間で効率的に行えることです。従来であれば担当者が一件ずつ電話をかけ、相手の応答を待つ時間がかかっていた督促やリマインド業務も、システムが自動で一斉発信することで作業時間を大幅に削減できます。特に支払い督促やイベント案内など、同じ内容を多くの顧客に伝える業務では効率化の効果が顕著です。
例えば、銀行などで変更手続きの促進をする場合、短期間で大量の顧客へ連絡する必要があります。期間限定のため人手が確保できず、オペレータの教育の時間も足りなくなります。そういった課題に対し、オートコールでリストに一斉に自動発信ができれば、人員調整なしで対応することも可能となります。実際に3週間で25万件リスト消化し、人件費70%削減した案件もあります。発信業務の効率化に課題がある場合には、オートコールの利用がおすすめです。
業務負荷の軽減
オートコールはオペレータの心理的・業務的な負担を大幅に軽減します。発信業務はオペレータにとって心理的にも負担の大きい業務だからです。
特に督促や案内といった反応の予測が難しい業務ではストレスもかかります。オートコールを活用すれば、定型的な連絡はシステムに任せられるため、スタッフは対応が必要な業務に集中できます。これにより人員の有効活用が可能となり、全体の業務効率も高まります。
オペレータを不要な架電から解放し、限られた人員を有効活用したいならオートコールの導入が適しています。
一定水準の品質維持
オートコールはオペレータの心理的・業務的な負担を大幅に軽減します。発信業務はオペレータにとって心理的にも負担の大きい業務だからです。
特に督促や案内といった反応の予測が難しい業務ではストレスもかかります。オートコールを活用すれば、定型的な連絡はシステムに任せられるため、スタッフは対応が必要な業務に集中できます。これにより人員の有効活用が可能となり、全体の業務効率も高まります。
オペレータを不要な架電から解放し、限られた人員を有効活用したいならオートコールの導入が適しています。
【部署別】オートコールを活用できるシーン
オートコールは幅広い部署で活用できる汎用的なツールです。単なる発信の自動化にとどまらず、以下の部署ごとに適した使い方があります。
- 営業
- カスタマーサポート
- マーケティング
それぞれ紹介していきます。
営業
-
リードへの追客・フォローコール
オートコールを使えば、録音済みの音声を一斉配信でき、効率的に接触頻度を高められます。担当者は反応があった顧客に集中できるため、商談機会の最大化につながります。
例えば、不動産のモデルルーム見学後に「ご興味はいかがですか?」と自動架電し、ボイスボットで「詳しく話を聞きたい」と答えた顧客だけをオペレータに転送する、といった活用が可能です。これにより、担当者は確度の高い見込み客に集中でき、効率的な営業活動が実現します。
キャンペーン・セミナー案内
展示会やウェビナーの案内、キャンペーン情報などを多くの顧客に届けたいときもオートコールは有効です。特に架電リストがある場合のオートコールは、オペレータによる架電と比べて3倍の生産性を実現した事例もあります。
カスタマーサポート
予約確認・リマインド通知
オートコールで事前に予約確認や来店リマインドを自動通知することで、病院・美容サロンなどで課題となるドタキャン防止と顧客のスケジュール忘れ防止の両方に寄与します。
督促・期限案内
オートコールは、料金の支払い督促や契約更新、サービス利用期限の案内にも活用できます。担当者が一件ずつ電話する負担を軽減でき、顧客にとっても必要な情報を確実に受け取れるメリットがあります。
マーケティング
顧客満足度調査
サービス利用後の顧客満足度を収集する際、オートコールで簡単なアンケートを実施する方法があります。短時間で多くの顧客の声を集められるため、施策改善の判断材料を効率的に得られます。
キャンペーン効果測定・市場調査
新商品の反応やキャンペーン効果を迅速に把握したい場合、オートコールを活用した調査が有効です。短期間でサンプルを収集できるため、意思決定のスピード向上に貢献します。
特に、使用する架電リストには無効なデータが含まれることが多く、従来は架電作業の負荷が大きく、相手先不在時には業務効率が低下するという課題がありました。しかし、オートコールを導入することで、無効なデータを自動で洗い出すリストクリーニング効果を実現できます。
さらに、見込み客と判断された場合には自動的に担当者に電話を転送する仕組みを組み合わせることで、人と連携して効果的にクロージングまで進めることが可能となります。この結果、効率的かつ精度の高いキャンペーン効果測定や市場調査を実現した事例があります。
オートコールを導入する際に気をつけたいこと
オートコールは効率化や業務負荷の軽減に大きな効果を発揮しますが、導入にあたって注意すべき点も存在します。特に以下の点を理解しておかないと、顧客体験の低下や期待した成果が得られない可能性があります。
- 顧客に不快感を与えるリスク
- 柔軟な対応ができない
- 応答内容に制約がある
それぞれ解説していきます。
顧客に不快感を与えるリスク
オートコールは録音音声、または機械音声を使用するため、受け手によっては機械的、一方的と感じられてしまうことがあります。特に頻度が多すぎたり、タイミングが適切でない場合は顧客満足度を損ねる要因になりかねません。配信リストや発信時間をしっかり管理することが重要です。
例えば、CRMに通話履歴が記録されるため、履歴を元に「直近1週間以内に架電した顧客を除外して発信する」といった運用を行うことで、通話率は改善し、クレーム発生も大幅に減少するでしょう。製品によってはこうしたリスト管理や発信制御機能が備わっているため、活用すると安心です。
柔軟な対応ができない
オートコールで架電してあらかじめ用意された録音やメッセージを流す形式では、顧客から想定外の反応があった際にその場で対応できません。例えば、追加の質問や特別な要望には対応が難しく、人によるフォローが必須となります。こうした制約を踏まえ、オートコールは一次対応や事前案内として位置づけるのが現実的です。
応答内容に制約がある
オートコールは基本的に一方向の通知が中心で、双方向のやり取りには限界があります。IVRを組み合わせればプッシュ操作による簡易応答、ボイスボットと組み合わせるなら会話での応答が可能です。
- 督促やリマインドの一斉通知ならオートコール
- 番号選択で部署振り分けならIVR
- 会話ベースで予約や詳細対応ならボイスボット
といったように業務に応じて使い分けることが効果的です。
オートコール導入で業務効率を高めるポイント
オートコールは正しく導入・運用すれば、業務効率を大きく改善できるツールです。ただし、導入時に確認すべき要素を見落とすと、十分な成果が得られなかったり、思わぬコスト増につながることもあります。
- 最大発信数を確認する
- 顧客に伝わる音声品質を重視する
- コスト構造をチェックする
- 必要な機能が揃っているか確認する
最大発信数を確認する
サービスによって同時に発信できる件数や、1時間あたりの最大発信数が異なります。発信件数の上限を把握せずに契約してしまうと、想定した規模での運用ができず効率化につながりません。自社の利用規模にあった発信数をカバーできるかどうか、必ず事前に確認しましょう。
顧客に伝わる音声品質を重視する
顧客にとって最も印象に残るのは音声の聞き取りやすさです。音質が悪かったりノイズが多いと、伝えたい情報が正しく届かず、かえって顧客の不満につながることもあります。録音方法や合成音声の自然さなど、顧客にストレスを与えない音声品質を確保することが重要です。
コスト構造をチェックする
オートコールの費用は、初期導入費用・月額利用料・通話料など複数の要素で構成されます。件数が増えるほどランニングコストが膨らむ仕組みもあるため、長期的にどの程度のコストになるかを試算しておく必要があります。短期的な安さだけでなく、トータルコストで比較検討しましょう。
必要な機能が揃っているか確認する
基本的な一斉発信機能に加え、発信結果のレポート機能や配信リストの管理機能などが備わっているかも重要です。これらが不足していると、運用効率が下がり、担当者の負担が逆に増えてしまうこともあります。自社の利用目的に応じて最低限必要な機能が揃っているかを見極めて導入することがポイントです。
また、画面のわかりやすさ、操作の手軽さによって日々の運用の手間削減にも繋がるため、使い勝手がよいUIかどうかも確認が必要です。
オートコール導入による発信業務の効率化をご検討中ならぜひご相談ください
本記事ではオートコールの基本情報やメリット、事前に注意しておく点を紹介しました。オートコールは、発信業務の効率化やオペレータの業務負荷の軽減といったメリットをもたらす一方で、顧客対応の柔軟性や体験価値という面では限界があります。
もし、通知やリマインドといった一方向の業務にとどまらず、顧客との自然な会話や柔軟な対応まで視野に入れているなら、AIボイスボット「commubo(コミュボ)」の導入をご検討ください。commuboなら、オートコールの効率性を活かしつつ、双方向のやり取りを自動化し、顧客体験を向上させることが可能です。
発信業務の効率化から、顧客満足度の向上まで一貫して支援できるソリューションとして、まずはお気軽にご相談ください。

commuboラボとは?
AIを活用した業務効率化×顧客満足向上を研究するメディアです。
今まで400社以上に電話応対自動化ソリューションを提供してきたソフトフロントが、自動化の考え方や、ボイスボット活用のコツ、お客様の活用事例、AI活用のトレンドなどをご紹介し、企業の生産性向上だけでなく、その先のお客様の顧客体験(CX)向上に役立つ情報を提供していきます。