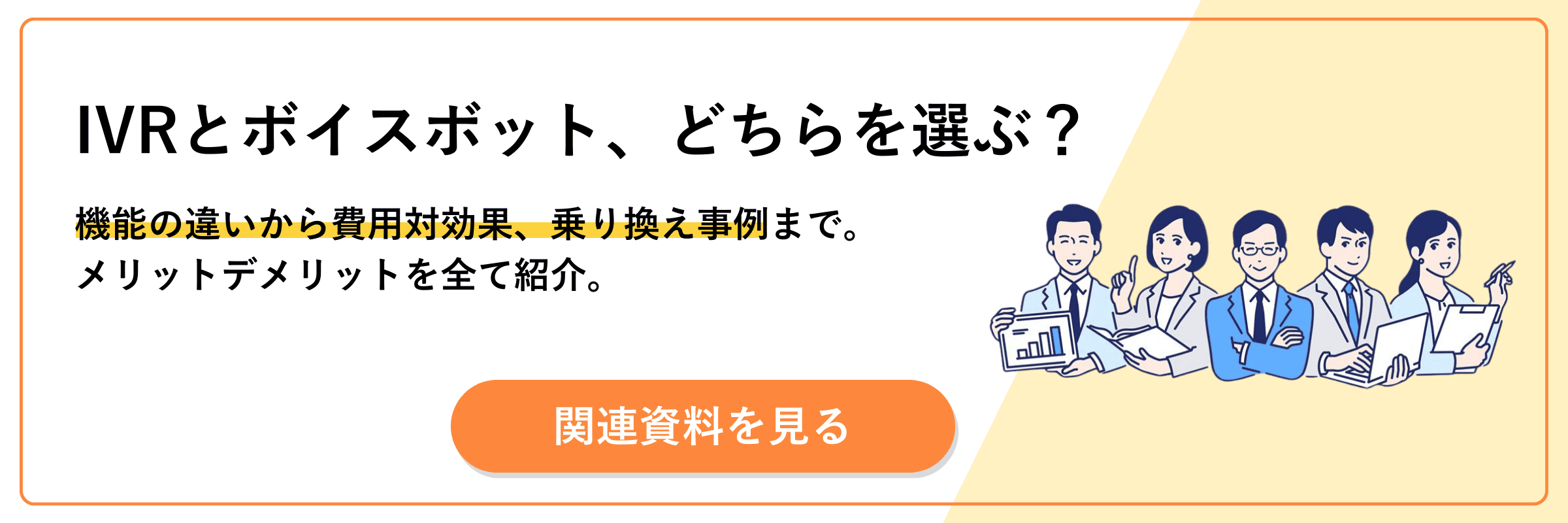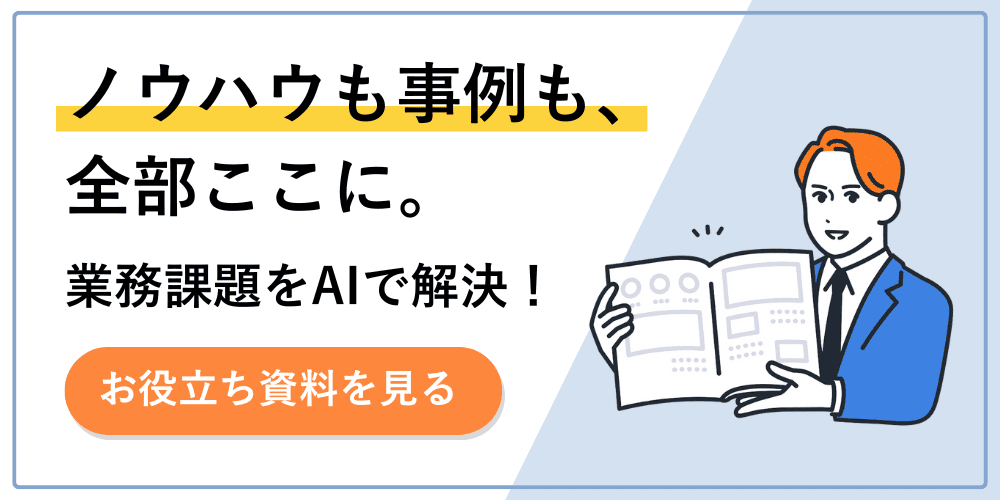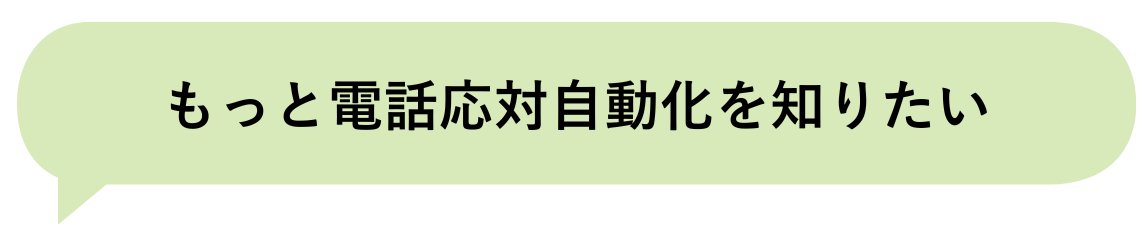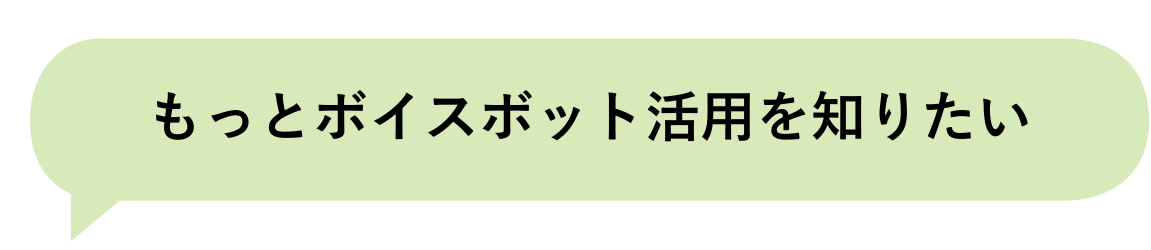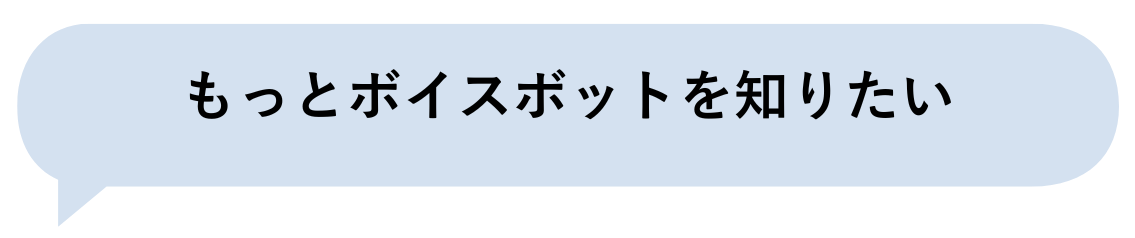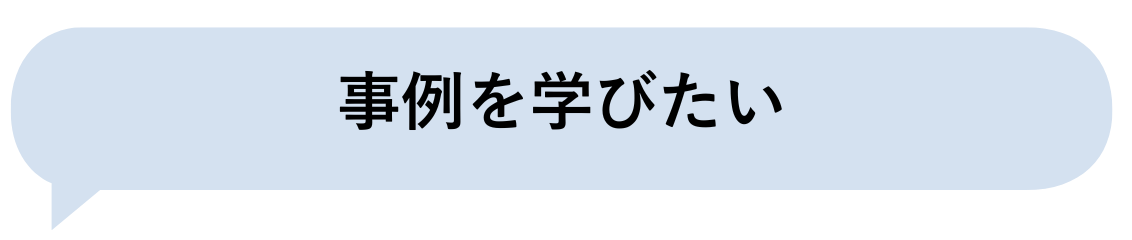IVRとは?電話自動振分けのメリットとコールセンター業務効率化事例
作成日:2025年10月1日 更新日:2025年10月1日

「コールセンターの入電が集中し、待ち時間が長くなっている…」
「夜間や休日の問い合わせに対応できず、機会損失が発生している…」
このような課題に悩まされていませんか?
実はIVR(自動音声応答)を導入することで、こうした負担やロスを効率的に解消できるのです。
この記事では、IVRの基本的な仕組みや、チャットボット・ボイスボットとの違い、導入による5つのメリット、注意点、活用事例などを詳しく解説します。
この記事を読めば、IVRによる業務効率化の全体像を理解し、自社に合った運用イメージが描けるようになります。応答品質と効率の両立を実現する第一歩として、ぜひご活用ください。
IVR(自動音声応答)とは
IVRとは自動音声が「○○の方は1を押してください」と案内をし、問い合わせ内容を振り分ける仕組みです。コールセンターや医療機関でよく活用されており、お客さまはスムーズに窓口につながり、企業は人手を有効に活用できます。
IVRの基本的な仕組み
着信があると自動音声が案内を流し、発信者は番号を押して希望の内容を選びます。その結果に応じて担当部署やサービスにつながる仕組みです。
さらに、CRM(顧客管理システム)と連携すると顧客情報や過去のやり取りを自動で照合でき、誤転送や同じ説明の繰り返しを減らせます。受付の品質を一定に保ちつつ、オペレータは複雑な案件に集中できるため、現場全体の応対効率が向上します。
IVRでできることと主な機能
IVRには以下のような機能があります。
- 顧客が自分で解決できるよう導くメニュー設計
- 担当部署への自動振り分け
- 営業時間外の自動案内
- 注文や予約の受付
- SMSでWebページへ誘導する機能
小規模な一次受付から始め、将来的にはCRMや音声認識と組み合わせて高度化できる拡張性も特徴です。
チャットボット、ボイスボットとの違い
まず結論として、IVRは電話回線での番号選択型案内、チャットボットはテキスト対話、ボイスボットは音声対話に強みがあります。
用途と操作方法が異なるため、目的に応じて使い分けることが重要です。
| 項目 | IVR(自動音声応答) | チャットボット | ボイスボット |
|---|---|---|---|
|
対応チャネル |
電話回線 |
Webサイト・アプリ・SNS |
電話・アプリ(音声認識) |
| 入力方法 |
プッシュ操作(番号入力) |
テキスト入力 |
音声入力 |
| 主な役割 |
問い合わせ内容の振り分け、一次案内 |
FAQ対応や手続き案内 |
FAQ対応、予約、決済など対話形式で完結 |
| 利用シーン |
コールセンター、医療予約、店舗受付 |
ECサイト、カスタマーサポート |
コールセンター、顧客対応の自動化 |
| 特徴 |
構造化された案内で効率化 |
ユーザーが自分のペースで操作可能 |
自然言語による会話形式で利便性が高い |
IVRは
- 電話対応が中心
- 定型パターンが多い
といったケースに適しています。
特に、問い合わせの一次振り分けや、営業時間外の自動案内を低コスト・短期間で導入したい企業には最適です。
一方でWeb中心のサービスや、高度な対話が求められる場合はチャットボット・ボイスボットのほうがフィットすることもあります。費用感や目的に応じて、最適な手段を選ぶことが、導入成功のカギとなります。
ボイスボットについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
ボイスボットとは?どこまで自動化できる?仕組み・メリット・活用事例を紹介
また、IVR・ボイスボット・オートコールの違いについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
IVRを導入するメリット5選
IVRを導入すると、以下のような複数の効果を同時に得られます。
- 業務効率化
- コスト削減
- 顧客満足度向上
- データ活用
- 24時間対応などの拡張性
それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
業務効率化:オペレータの負担軽減
IVRは、日常的な確認や取次を自動化し、オペレータの対応負荷を大きく軽減できます。
確認作業や部署への転送といった定型対応をシステムが担うことで、スタッフは複雑な案件や感情配慮が必要な対応に専念できるようになります。
特に入電が集中する時間帯でも処理の滞りを防ぎ、応答品質を安定させる効果があります。
例えば問合せ内容に応じて詳しい担当者に振り分ける設定をすることで、ばらつきのある対応を抑え、平均対応時間の短縮にもつながります。結果として、組織全体の生産性を向上させることが可能です。
コスト削減:人件費・運営コスト
IVRは、人手に依存していた受付業務を自動化し、運営にかかるコストを削減できます。
クラウド型のIVRは、初期投資が少なく、段階的な導入からスタートできます。問い合わせ件数が増加する繁忙期の対応も柔軟に行えます。
顧客満足度向上:待ち時間を短縮
IVRは、利用者を適切な窓口へ素早く誘導することで、待ち時間の短縮に貢献します。
「何度も転送された」「待たされた」という不満は、顧客体験を大きく損ねる要因です。IVRを活用することで、こうした課題を回避しやすくなります。
SMS連携を活用すれば、手続きやFAQページへの誘導も可能です。これにより自己解決率が上がり、通話時間や再度の問い合わせ件数も減少します。
混雑時でもサービス品質を保ちながら、お待たせしない対応が実現できるのは大きな強みです。
加えて、適切な窓口に素早くつながることで、通話時間が短くなり、顧客のストレス軽減にもつながります。
データ活用:問い合わせデータ収集・分析
IVRは、顧客の選択履歴や通話データを蓄積し、業務改善に活かすことができます。
例えば、良く選ばれているメニューや時間帯などの情報を定量的に把握することで、業務配分や人員配置の見直しにつながります。
また、人気サービスや問い合わせ傾向が可視化されれば、新しい商品展開や施策にも応用できます。単なる受付システムにとどまらず、マーケティングや業務戦略に活かせる情報基盤にもなるのがIVRの魅力です。
24時間365日の対応が可能になる
IVRを導入すれば、夜間や休日を含む24時間体制の対応が可能になります。これまで対応できなかった時間帯に自動音声で案内することで、取りこぼしや機会損失を防ぐことができます。
また、問い合わせを受けた後に「重要な案件のみメール通知する」といった運用も可能なため、翌営業日にスムーズな対応へとつなげられます。時間に関係なく顧客が問合せできることは、利便性の向上だけでなく、企業への信頼感を高める要因にもなります。
24時間対応のコールセンターの構築について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
IVR導入の注意点・デメリット4選
IVRは多くの業務課題を解決する優れた仕組みですが、導入や運用を誤ると逆効果になりかねません。
ここでは特に注意すべき4つのポイントを解説します。
- 複雑すぎるメニューは逆効果
- コストがかかる
- 更新・改善を怠ると陳腐化する
- 高齢者やITに不慣れな人にとってハードルが高い場合がある
それぞれ紹介していきます。
複雑すぎるメニューは逆効果営業
IVRは案内が複雑すぎると、かえって顧客の混乱やストレスを招いてしまいます。選択肢が多すぎたり、何度も番号入力が必要になると「面倒」「わかりにくい」といった不満につながります。
実際「何度も番号を押す羽目になった」「目的の部署にたどり着けなかった」という声は、IVRに対する代表的なネガティブな印象の一つです。導入の際は、直感的に操作できる構成を意識し、最小限の選択肢でスムーズに誘導できる設計が求められます。
コストがかかる
IVRの導入には、初期費用や月額利用料など、ある程度のコストがかかります。特にクラウド型の場合でも、基本料金に加え、カスタマイズや外部システムとの連携には追加費用が発生するケースがあります。
しかし、これらの支出は長期的な人件費や採用・教育コストと比較することで、その妥当性が見えてきます。オペレータの配置・育成にかかるリソースと天秤にかけたとき、IVRはむしろ効率化のための合理的な投資として評価されるべきです。
更新・改善を怠ると陳腐化する
IVRは一度導入すれば終わり、というものではありません。時間が経てばサービス内容や業務フロー、顧客のニーズは変化します。それにも関わらず、メニューや案内が昔のままだと、誤案内や無駄な手間が生じる原因になります。
「在庫切れの商品を案内し続けていた」「すでに廃止された部署が選択肢に残っていた」などの事例も報告されています。IVRの品質を保つには、定期的なログ確認やメニュー構成の見直しなど、継続的な改善運用が不可欠です。
高齢者やITに不慣れな人にとってハードルが高い場合がある
Webサイト検索やチャットと比べ、電話チャネルを活用したIVRはIT活用に不慣れな方には使いやすくはありますが、番号入力や音声案内に慣れていない人にとっては使いにくいシステムと感じられる場合があります。特に高齢者層は、デジタル操作に不安を感じる傾向が強く、音声の聞き取りづらさや操作中の不安感がストレスにつながることもあります。また、スマートフォンを利用の場合、プッシュ画面の表示方法がわからないというケースもあります。
このようなケースでは「途中で切ってしまった」「結局オペレータにつなげなかった」といった問題が発生します。そのため、シンプルな操作設計や、途中で「担当者へつなぐ」選択肢を残しておくなど、利用者目線での配慮が必要です。
IVRの活用事例
IVRは業種・規模を問わず、さまざまな現場で導入が進んでいます。ここでは代表的な活用例として、以下の事例を紹介します。
- 着信自動振り分けと録音で応対精度を高め、業務負荷を軽減
- 応答率14%から91%へ。IVRと自動応答で業務効率と品質を向上
着信自動振り分けと録音で応対精度を高め、業務負荷を軽減
従来の体制では、問合せ内容が事前にわからないため、新人オペレータは最初から全てに応対できるスキルを身に着ける必要があり、育成に時間がかかっていました。。IVRを使って着信を内容に応じて振り分けることで、新人オペレータは範囲を制限して応対を進めることができ、負担軽減を実現しました。また、自動応答で一部応対を自動化することで、業務効率もさらに向上しています。
応答率14%から91%へ。IVRと自動応答で業務効率と品質を向上
電話注文が殺到するだけでなく、注文以外の問合せも多く、窓口に混乱が生じていました。IVR(自動音声応答)や自動応答機能を活用し、効率的な受電体制を実現することで、応答率が最大91%まで向上し、業務効率と応対品質の向上が達成されました。
IVRの種類と費用相場
IVRには大きく分けてオンプレミス型とクラウド型の2種類があります。
オンプレミス型は自社内にサーバーを設置し、自社の業務にあわせて柔軟なカスタマイズが可能ですが、その分初期投資が高額になる傾向があります。
一方で、クラウド型はインターネット経由で提供されるサービスで、初期費用を抑えて導入できることが特徴です。月額課金制で利用でき、スモールスタートにも適しています。
導入コストの相場としては、クラウド型は月額1万〜10万円程度が一般的で、オンプレミス型は規模や機能により数百万円かかる場合もあります。
どちらを選ぶべきかは、自社の予算やIT体制、今後の運用方針をふまえて慎重に検討することが重要です。
IVR活用で応答品質と効率を最大化できる
IVRは業務負担の軽減、コスト削減、待ち時間の短縮、24時間対応など、多くのメリットが得られます。一方で、複雑なメニュー構成や定期的な見直し不足、高齢者への配慮不足といった課題も存在します。
ソフトフロントでは、こうしたIVRの課題を解決できるAIボイスボット「commubo(コミュボ)」を提供しています。IVRの機能も持ちながら、さらに自然な会話での音声案内、柔軟な運用設計、導入後の改善支援まで一気通貫で対応可能です。IVRでは難しかった柔軟な対話設計や、CRMとの高度な連携も実現できます。
IVRとcommuboの違いはこちらの資料も併せてご覧ください。

commuboラボとは?
AIを活用した業務効率化×顧客満足向上を研究するメディアです。
今まで400社以上に電話応対自動化ソリューションを提供してきたソフトフロントが、自動化の考え方や、ボイスボット活用のコツ、お客様の活用事例、AI活用のトレンドなどをご紹介し、企業の生産性向上だけでなく、その先のお客様の顧客体験(CX)向上に役立つ情報を提供していきます。