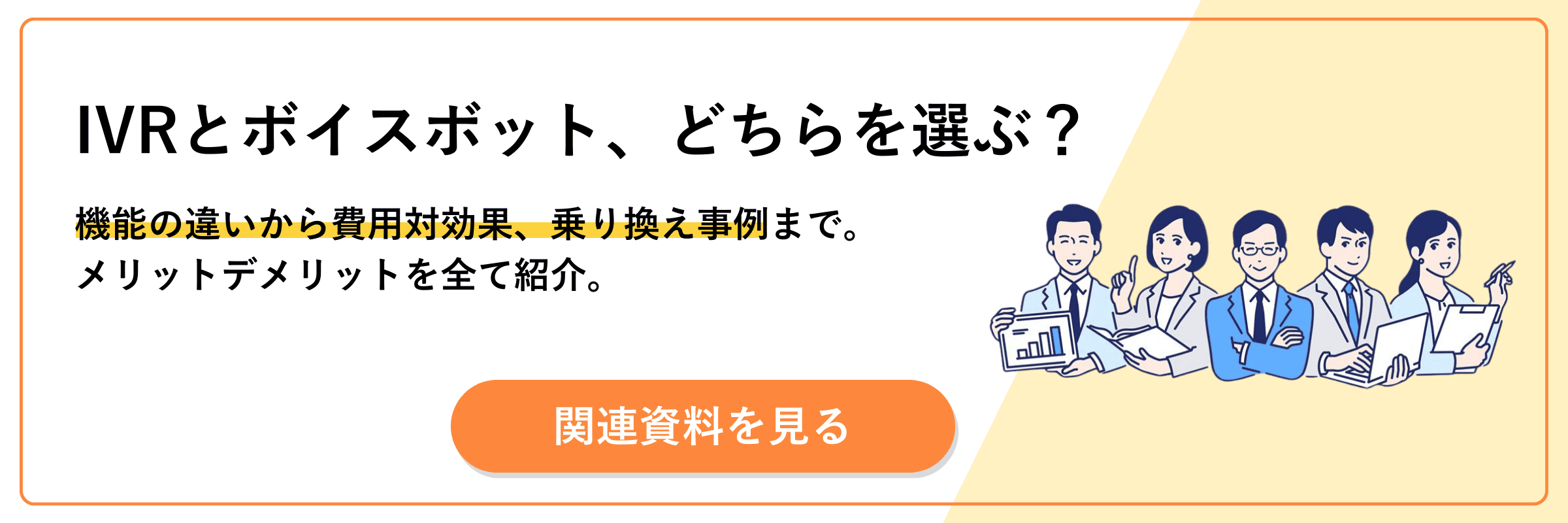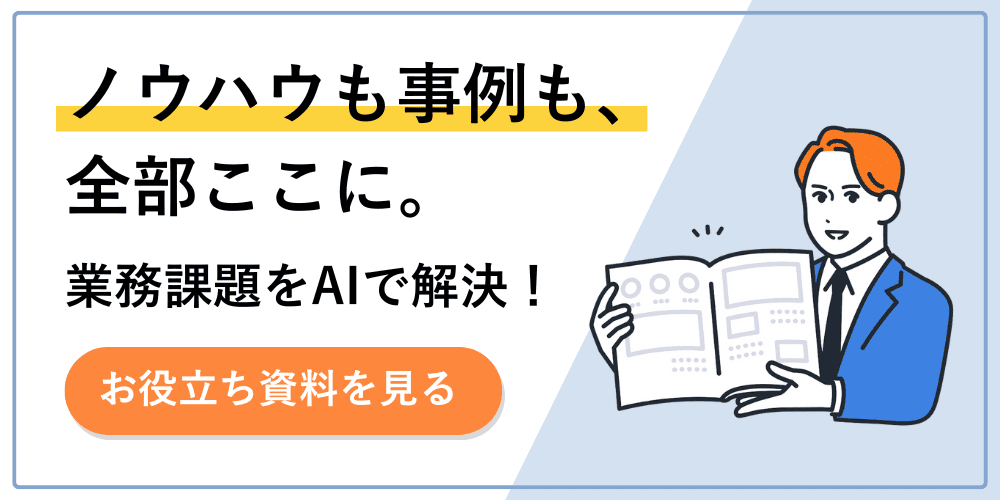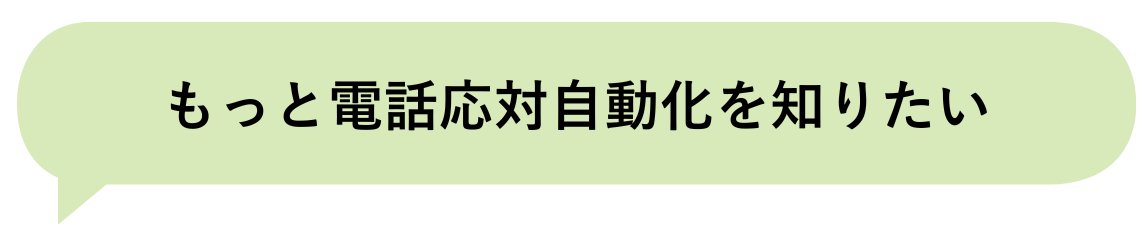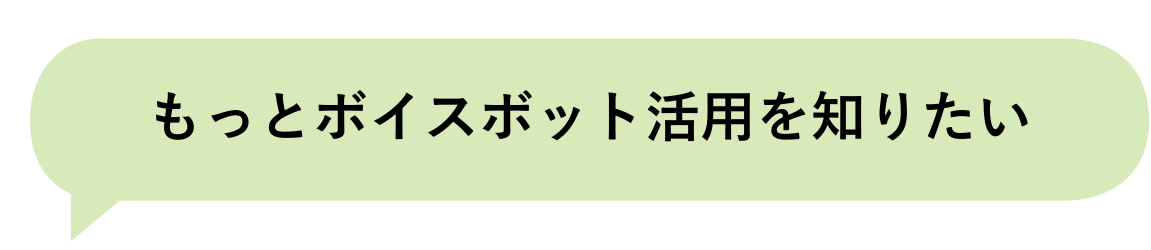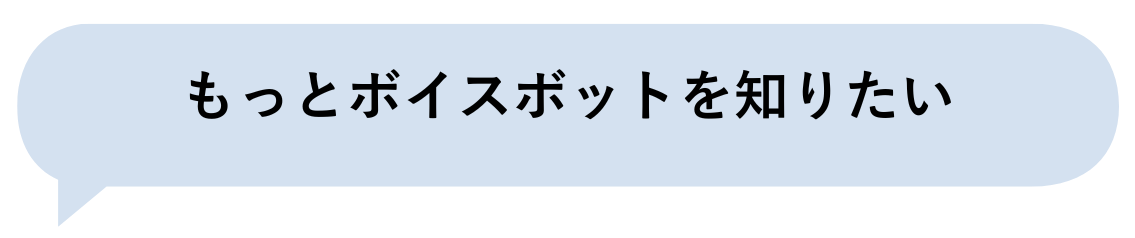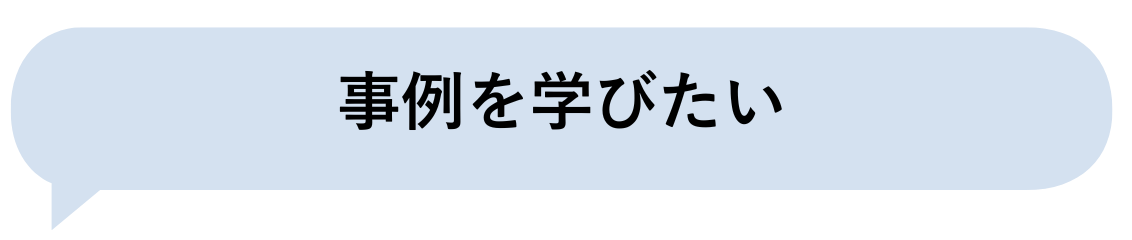オートコールとは架電業務を自動化するシステム!メリットや活用シーンを解説
作成日:2025年10月1日 更新日:2025年10月1日

「顧客対応の質を上げたいのに、電話とPC作業が分断されて効率が悪い」
「問い合わせが増えると、対応のムラや待ち時間が発生してしまう」
このようなコールセンター業務の非効率さに悩んでいませんか?
実はPCと電話を連携させるCTIシステムを導入することで、業務効率化と顧客満足度の両立が実現できます。
この記事ではCTIの基本機能や導入メリット、実際の活用事例について解説します。コールセンターの業務効率化と顧客満足度向上に役立ててください。
コールセンターの自動化について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
CTIとは?電話業務効率化に繋がる機能
まずはCTIの基本的な仕組みと、導入することでどのようなことが可能になるのかを確認しましょう。
- CTIとは
- CTIの導入でできること
CTIとは
CTI(Computer Telephony Integration)とは、電話とコンピューターを連携させる仕組みです。着信・発信・通話制御や履歴記録を画面上で一元管理できるため、オペレータは状況を把握した上でスムーズに会話を始められます。
CTIの導入でできること
CTIを導入すると、以下のようなことができます。CTIは基本的にはPCと電話の連携ですが、システムにより、様々な便利な付加機能が用意されています。
-
【基本機能】
- 着信・発信制御:オペレータがPC上で電話操作可能
- 通話履歴の記録:通話時間・担当者・内容を自動保存
- オペレータ状況把握:稼働状況や対応件数を管理者が確認可能
-
【付加機能】
- 着信ポップアップ:顧客情報や過去の対応履歴を画面に表示
- 通話録音・保存:全通話を記録し、教育やトラブル防止に活用
- CRM連携:Salesforceやkintoneと連動して顧客データを一元管理
- モニタリング:リアルタイムで通話状況を確認・指導可能
- 統計・分析:応答率やキーワード分析で業務改善
- スマホ対応:在宅勤務や外出先でも会社番号で発着信可能
これらを組み合わせることで、効率化・品質向上・働き方の柔軟性を同時に実現できるのがCTIの強みです。
コールセンターにCTIを導入するメリット
CTIの導入によって得られる効果は多岐にわたります。ここでは代表的な3つのメリットを紹介し、それぞれの活用シーンや効果を解説します。
- オペレータ業務の効率化
- 顧客対応の質向上
- 管理と運営の最適化
- 在宅・BCP対策
オペレータ業務の効率化
CTIを導入することで、オペレータ業務を効率化できます。
従来の電話機操作では、着信・発信・転送といった作業が複雑で、操作手順の確認やボタンの押し間違いなどによって対応時間が増加したり、通話の取りこぼしや誤転送といったミスの要因となったりしていました。
CTIを利用することで、これらの作業をPC上で直感的に行えるようになり、業務効率が大幅に改善されます。
例えば、保留や転送などをワンクリックで操作を簡略化したり、適切なオペレータに着信を自動で割り当てすることができたりします。
以上のように、CTIの導入は単に業務を楽にするだけではなく、応答率や処理件数の改善を通じて、コールセンター全体の業務効率化が可能です。
顧客対応の質向上
CTIを導入することで顧客対応の品質を向上させることができます。
CTIは、CRMなどのシステムと連携することで、電話が鳴った瞬間に顧客情報をポップアップ表示でき、オペレータは相手の名前、契約内容、過去のやり取りを把握した状態で会話を始められるためです。
顧客にとっては「自分の状況を理解してもらえている」という実感があり、冒頭からスムーズに本題へ入れるため、無駄な説明や確認に時間を費やす必要がありません。
また、過去のクレームや要望履歴も参照できるため、対応の一貫性が保たれ、担当者が変わっても同じ品質でサービスを受けられるようになります。
管理と運営の最適化
CTIを導入することで、管理と運営の最適化を図ることができます。
CTIには、通話履歴やオペレータの稼働状況を自動的に記録・集計する機能が備わっており、管理者は、誰が何件の対応をしているのか、応答時間や放棄呼がどの程度発生しているのかをリアルタイムに把握できます。
従来であれば人手で集計しなければならなかったデータが自動化されることで、運営上の負担が軽減されるだけでなく、客観的な指標に基づいたマネジメントが可能になります。
例えば、データを分析することで人員配置の偏りを是正したり、特定のオペレータに負荷が集中しないように調整したりできます。
管理者の経験や勘で管理していた内容を、CTIのデータ管理により、最適化することが可能です。
在宅・BCP対策
コールセンターにCTIを導入することで、在宅勤務やBCP(事業継続計画)対策を強化でき、災害時や緊急時でも業務を継続しやすくなります。
CTIはクラウド型で提供されることが多く、インターネット環境とPCがあればどこからでもアクセス可能です。そのため、拠点に依存せずに在宅勤務や複数拠点での業務分散が可能となります。
実際に、IVRや自動応答機能と併用することで受電体制が効率化され、応答率の大幅な向上と業務効率の改善が実現した事例もあります。
このように、CTIの導入は在宅勤務やBCP対策を後押しし、非常時でもコールセンター業務を安定して運営することに寄与します。
業務が効率的になる!CTIの3つの機能
CTIには数多くの機能がありますが、ここでは特にコールセンターの現場で効果を発揮する3つの代表的な機能を紹介します。
- オペレータ個別対応を支援するリアルタイムモニタリング
- CRMとの連携機能
- 稼働状況管理機能
オペレータ個別対応を支援するリアルタイムモニタリング
モニタリング機能は、管理者がオペレータと顧客の通話をリアルタイムで確認できる仕組みです。オペレータが対応中の会話内容や進行状況を即座に把握できるため、個別の支援が可能になります。
さらに、チャットやささやき機能を使えば、顧客に気付かれずにオペレータに指示やアドバイスを送ることができ、個別対応の精度と迅速性を高めます。この機能は、オペレータが1件1件の顧客対応を効率的かつ正確に行えるように支援する役割を果たします。
CRMとの連携機能
CRMとの連携機能は、CTIが持つ代表的な機能であり、顧客対応の効率を大きく高めます。
CRM連携により、着信と同時に顧客情報がPC画面に自動表示され、基本情報だけでなく購入履歴や過去の問い合わせ内容など、CRMに保存されているあらゆるデータが参照できます。
その結果、オペレータは通話開始の時点から顧客の状況を把握したうえで対応でき、さらに通話記録はCRMに自動反映されるため、手作業で入力する負担もなくなります。
このように、CRM連携機能は顧客情報を一元管理し、迅速かつ正確な対応を可能にする重要な仕組みです。
稼働状況管理機能
稼働状況管理機能は、オペレータ全体の稼働状況をリアルタイムで把握できる仕組みです。通話中・待機中のステータス、対応件数、平均通話時間などのデータを自動で集計し、管理画面から一目で確認できます。
全体の応答状況や業務負荷の偏りを即座に把握し、適切なオペレータ配置や応答遅延の改善に役立てられます。さらに、蓄積データを分析することで、コールセンター全体の処理能力や応答率の傾向を把握し、業務改善や効率化の施策に活かせます。この機能は、コールセンター全体の管理と最適化を支える重要な役割を果たします。
CTIはこう使われている!業界別の活用事例紹介
実際にCTIが導入されている業界では、どのような課題が解決され、どのような成果が出ているのでしょうか。ここでは以下の事例を紹介します。
- インフラ
- 銀行
- BPO
インフラ
| ツール名 | コミュニケーション方法 |
|---|---|
|
課題 |
従来のオンプレ型PBXでは、設備更新時の費用、災害・停電時等のBCP対策、働き方変革への対応という課題があった。 また、少人数体制での応答率維持や繁忙期対応、オペレータの負荷軽減が困難で、自動化を求めていた。 |
|
成果 |
クラウド型CTIの導入により、在宅からでも勤務できる体制を構築できた。 また、AIボイスボット「commubo(コミュボ)」と連携することで、定型問い合わせの自動応答が可能となり、応答率を維持しながら、オペレータは複雑な対応に集中できるようになった。 |
導入事例:コールセンター体制強化で経営課題解決に貢献、ポイントはシナリオのカスタマイズ性・BIZTEL連携・スピード感
ボイスボットとは何かやボイスボットの導入事例について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
銀行
| ツール名 | コミュニケーション方法 |
|---|---|
|
課題 |
従来のオンプレ型PBXは老朽化により多額のコストが発生していた。 また、顧客情報や受電状況の把握に時間がかかり、聞き直しなどが発生していた。 |
|
成果 |
合併に伴いクラウドCTIへ移行。CRM連携で着信と同時に顧客情報が表示されるため、問い合わせ対応のスピードが格段に向上した。 また、ステータスモニタリング機能によりコミュニケーターの待機状況や次の受電順が可視化され、業務効率化と負荷分散が実現。迅速な応対が可能になり、顧客満足度向上とコミュニケーターの業務管理負担の軽減につながった。 |
BPO
| ツール名 | コミュニケーション方法 |
|---|---|
|
課題 |
従来のオンプレミスPBXを基盤としたシステムでは、テレワーク環境の整備に時間がかかり、VPN接続やソフトフォンの導入、ライセンス管理などが必要で、システム運用に負担が集中していた。 また、営業時間変更や外部システム連携にも多くの管理工数がかかり、オペレータやエンジニアの負荷が高かった。 |
|
成果 |
インターネット環境さえあればオフィスと同じシステムを利用できるようになり、テレワークへの切り替えが迅速かつ容易になった。 設定面の内製化が進み、エンジニアの負荷が軽減された。また管理面でもCTIのダッシュボード機能により、センター内の稼働可視化、コミュニケーターごとのスコアリングなどを活用した管理の効率化などを実現し、従業員満足度向上や離職率低減にもつながった。 |
自社に合ったCTIの選び方を解説
CTIと一口に言っても、提供ベンダや機能はさまざまです。自社に最適なシステムを選ぶために、確認すべき3つのポイントを紹介します。
- 自社に必要な機能を提供しているか
- 既存システムと連携ができるか
- スマートフォンに対応しているか
自社に必要な機能を提供しているか
1つ目は、自社に必要な機能を提供しているかです。
CTIには通話録音やIVR、着信振り分け、通話ログ管理など多数の機能がありますが、すべてを盛り込むとコストが高くなり、運用も複雑になります。
まずは自社に必要な機能と将来的に必要になるかもしれない機能を整理しましょう。例えば、教育強化を目的とするならモニタリング・録音機能を重視し、CRM活用を重視するならポップアップ機能を備えたシステムを選ぶべきです。
既存システムと連携ができるか
既存システムと連携できるかどうか確認しましょう。
コールセンターは単独で業務を完結するわけではなく、営業やマーケティング部門と情報を共有する必要があります。
Salesforceやkintone、HubSpotなどのCRMやSFAと連携できれば、顧客データを一元管理でき、商談や販促活動にも役立ちます。
逆に、連携が不十分だと「CTIに蓄積したデータを有効活用できない」という事態に陥ることもあるため、事前確認は必須です。
スマートフォンに対応しているか
在宅勤務やフリーアドレス、外回り営業など、オフィス以外で業務を行うスタイルが一般化してきました。スマホ対応のCTIを導入すれば、オフィス外からでも会社の代表番号で発着信が可能になります。
例えば、外出先で急な問い合わせを受けても、即時に折り返すことができ、対応スピードの向上につながります。
業務効率化と人材不足の解消を実現しよう
CTIは電話とPCを連携させることで、コールセンターの効率化と品質向上を実現するシステムです。
録音・モニタリング・CRM連携といった機能を活用することで、顧客満足度とオペレータの働きやすさを両立できます。
ただし、CTI単体では効率化止まりで人手依存から完全に脱却するのは難しいのも事実です。
人手不足やDXといった文脈でコールセンター業務の改革を進めるなら、AIボイスボットの活用がおすすめです。
AIボイスボットは問い合わせ内容を理解し、適切な案内ができるため、一次対応がシステムで完結します。
CTIと内線接続ができるAIボイスボットを組み合わせることで、無人対応と有人対応の最適分担が可能になり、業務効率化と顧客満足度向上を同時に実現できます。
ボイスボットについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
ボイスボットとは?どこまで自動化できる?仕組み・メリット・活用事例を紹介
人材不足や応答率低下に悩むコールセンター運営者の方は、AIボイスボット「commubo(コミュボ)」の導入もご検討ください。各種CTIとも連携し、スムーズな自動化導入を実現することができます。
commuboの連携検証済CTI/PBXシステム一覧はこちら。

commuboラボとは?
AIを活用した業務効率化×顧客満足向上を研究するメディアです。
今まで400社以上に電話応対自動化ソリューションを提供してきたソフトフロントが、自動化の考え方や、ボイスボット活用のコツ、お客様の活用事例、AI活用のトレンドなどをご紹介し、企業の生産性向上だけでなく、その先のお客様の顧客体験(CX)向上に役立つ情報を提供していきます。