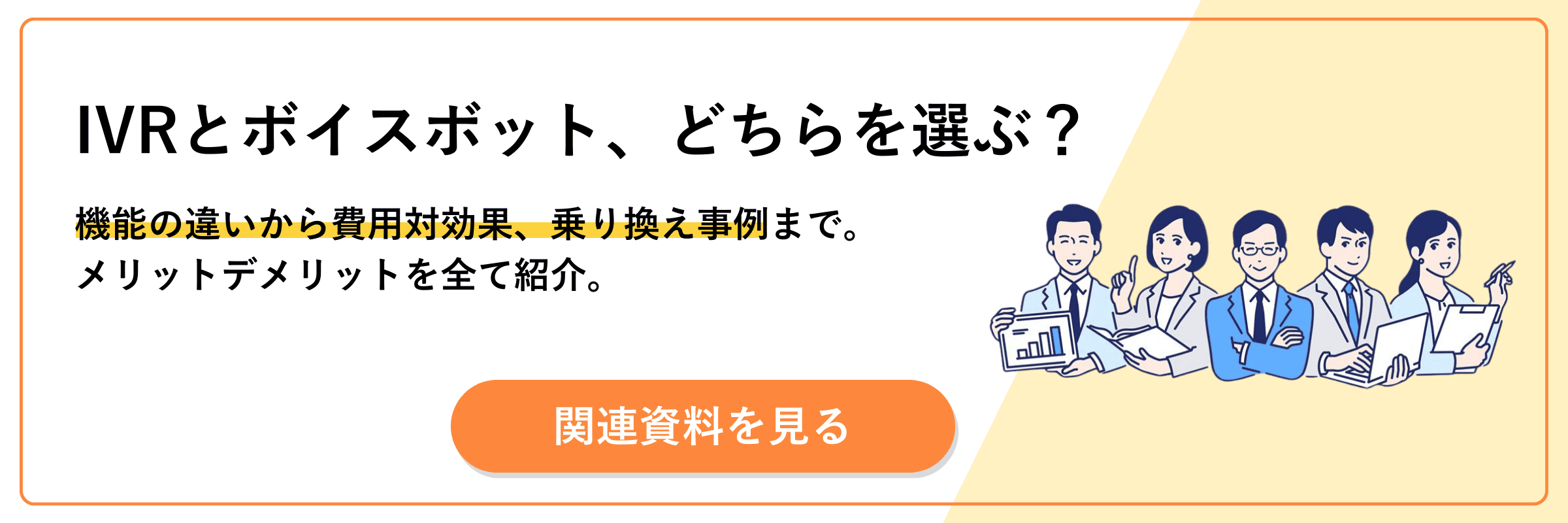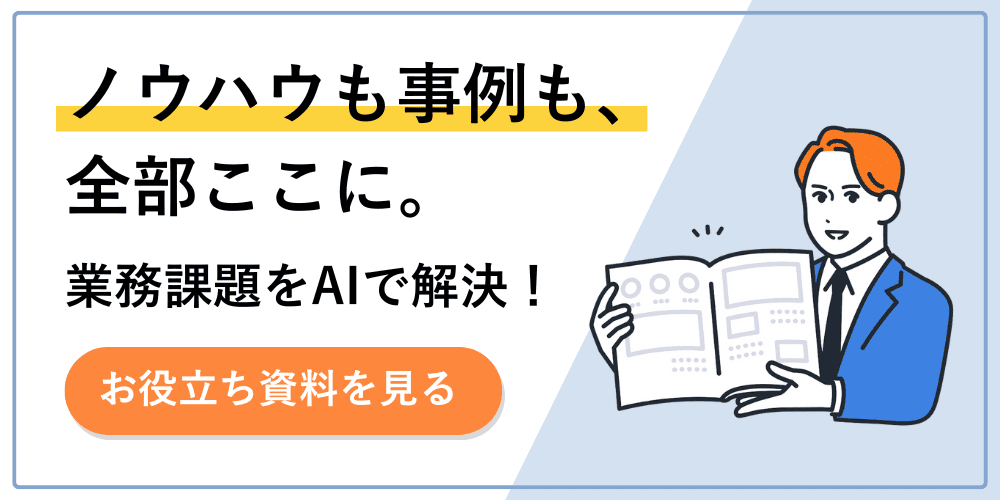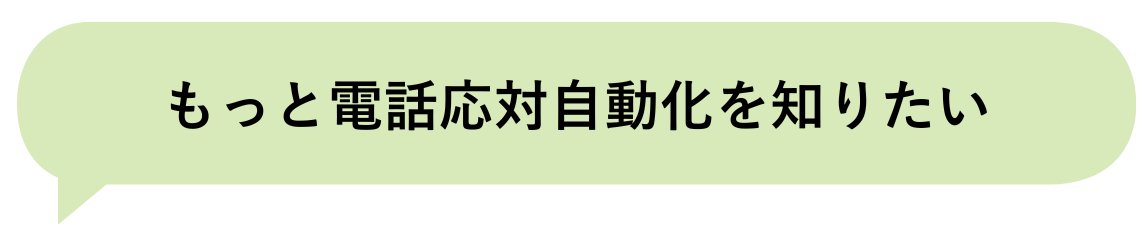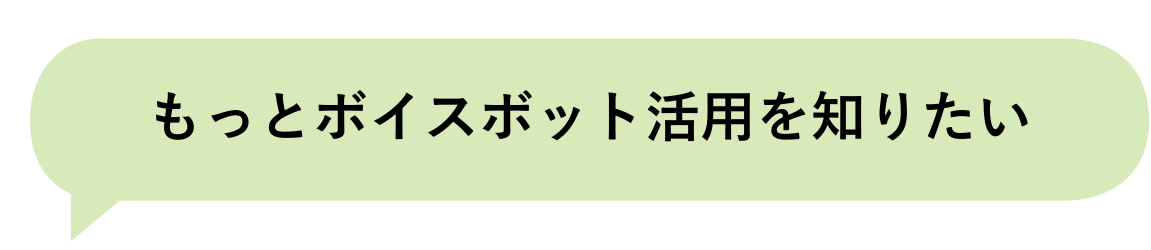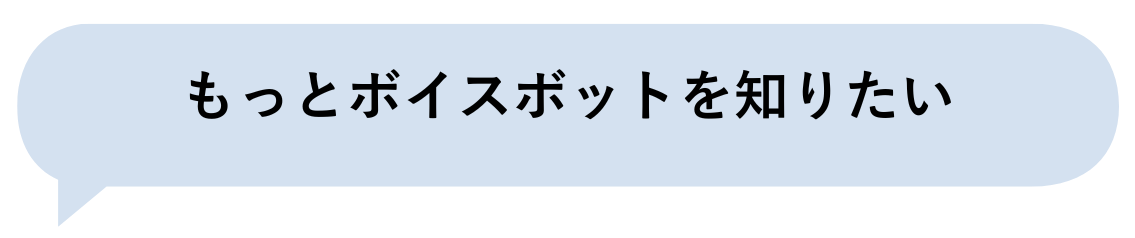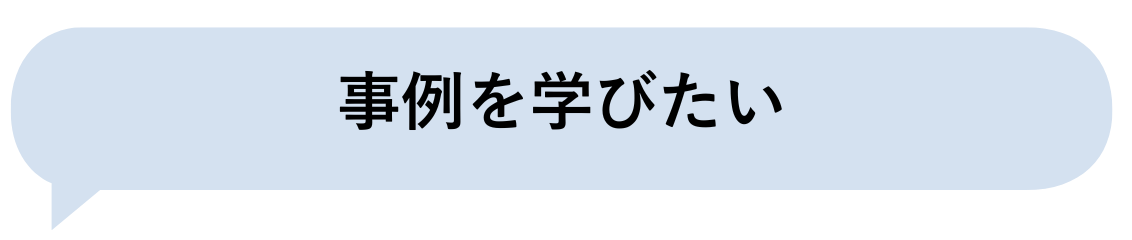電話応対を自動化するには?導入手順や活用事例を紹介
作成日:2025年10月1日 更新日:2025年10月1日

現代のビジネス環境で、顧客からの問い合わせ対応は企業の重要な業務のひとつです。
電話応対は正確かつ丁寧に行う必要がありますが、人手不足や業務負荷の増加により、対応の効率化が求められています。
電話応対の自動化を活用することで、応対時間の短縮や24時間対応の実現、オペレーターの負担軽減などさまざまなメリットが得られます。
本記事では、電話応対を自動化するための導入手順や活用事例について紹介します。
電話応対の自動化を検討している方や自動化ツールの導入手順について詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
電話応対業務で活用できる主な自動化・効率化ツール3つ
電話応対業務は、ボイスボット・チャットボット・IVRの活用で自動化・効率化の推進が可能です。
各ツールの概要と、メリット・デメリットについて詳しくみていきましょう。
ボイスボット
ボイスボットとは、AI自動応答システムを活用した音声システムのことです。
顧客の問い合わせをAIが聞き取り、内容を認識して対応を行うまでの流れを一貫して行えます。
ボイスボットは、自然な会話の流れで顧客との対応が行えるメリットがあります。
また、問い合わせに対し人間の声で応答でき、音声の性別や想定年代などもあらかじめ設定することで場に適した会話の雰囲気を作り出すことも可能です。
そして、会話でやり取りが完結できるため、問い合わせた顧客は何か入力したり操作したりする作業が不要で、利便性が高い手法になります。
ただし、複雑な内容の問い合わせ対応には向いていないため、オペレーターとの役割を切り分けて活用すると良いでしょう。
チャットボット
チャットボットとは、チャットとロボットを組み合わせたものでAIや自然言語処理の技術を活用して、テキストにて顧客の対応を行うシステムです。
Webサイトや問い合わせチャットから寄せられる問い合わせに対し、適切な回答を生成してテキスト化して回答します。
チャットボットは文字入力により回答を得られるため、問い合わせから商品検索、予約受付などのニーズに対応可能で、多様な問い合わせチャネルに活用されています。
しかし、質問を文字や項目入力するため、人によっては煩わしく感じられるかも知れません。
IVR(自動音声応答システム)
IVR(自動音声応答システム)とは、顧客の問い合わせに対して音声ガイダンスで案内を行い、プッシュボタンで選択・入力してもらうことで一次対応やオペレーターへの取次などを行うシステムです。
顧客が知りたい内容や手続きしたい内容を一次対応の時点でカテゴライズされるので、オペレーターに取次される時点である程度問い合わせ内容が把握できる状態で顧客対応できます。
ただし、急いでいる顧客にとってはオペレーターにつながるまで時間を要するため、ストレスに感じてしまう可能性があります。
IVRについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
IVRとは?電話自動振分けのメリットとコールセンター業務効率化事例
また、IVR・ボイスボットの違いについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
電話応対における顧客対応の自動化・効率化推進のポイント4つ
電話応対において、顧客対応の自動化・効率化ができれば、人材不足や機会損失の解消だけでなく、品質の均一化にも効果的です。
顧客対応の自動化・効率化をスムーズに推進するためのポイント4つについて、詳しくみていきましょう。
初期対応や定型的なフローから導入する
電話応対における顧客対応の自動化・効率化は、初期対応や定型的なフローから導入を試みましょう。
コールセンターでは、人員不足やあふれ呼などによる機会損失や顧客満足度の低下が課題となっている一方で、自動化ツールは一挙に複数の顧客対応が可能なため、
導入段階では、まずは呼量が多く、かつ定型的な内容の応対業務から始めるのがおすすめです。
複雑な問題解決やカスタマイズされた対応が求められる業務は、オペレーターが対応するというように業務を切り分けて進めていくと良いでしょう。
一部の業務から自動化を採用してみる
電話応対の自動化をはじめから業務全体で導入しようとすると、想定したよりも効果が得られず疲弊してしまいます。
一次受付から担当部署への取次、相手先の名前や連絡先を聴取するスナッチ対応などの一部業務から自動化を採用してみましょう。
ミニマムに始めることで早く効果が現れるとともに、運用に慣れることで段階的に自動化・効率化が進めやすくなります。
また、外部システムとのデータ連携についても、一部業務から進めることで検証しやすくなるでしょう。
顧客対応の自動化における導入効果を数値化する
顧客対応の自動化により導入効果がどのくらいあるのかについては、数値化することで客観的な評価が可能になります。
コールセンター管理に活用されるKPIとしては、応答率や放棄呼率などのつながりやすさといった接続品質を測定する項目です。
オペレーター管理に活用されるKPIとしては、平均通話時間(ATT)や平均後処理時間(ACW)などのオペレーターの対応速度といった生産品質を測定する項目です。
これらの項目を分析し、顧客対応の自動化における導入効果を評価して、課題をあぶり出し改善点を実践すると、自動化が可能な業務の範囲が広がってくるでしょう。
他にも、顧客から寄せられる商品やサービスに対する要望・意見からサービスの品質向上を行うVOC分析も導入効果を数値化するのによく用いられています。
電話応答で自動化する業務の改善・拡張を定期的に行う
電話応答で自動化する業務は、導入段階では一部の業務に限定して稼働時間や対象を絞って進めることで効果を検証していきます。
そして、ある程度自動化が定着してきた段階で、改善点の実践や自動化する業務の拡張を定期的に行いましょう。
例えば、稼働時間を徐々に拡張してみたり、よく問い合わせのある内容については回答できるようシナリオ追加してみたりするのも良いでしょう。
自動化する業務について、定期的に改善・拡張することでより効率化が推進できます。
顧客対応の自動化の活用事例4つ
顧客対応の自動化では、具体的にどのような活用法があるのでしょうか。ここでは、活用事例について4つ紹介しましょう。
自治体やメーカーなどの一次対応
顧客対応の自動化で代表的な活用事例として、自治体やメーカーなどへの問い合わせ対応に対する一次対応の自動化です。
自治体やメーカーに寄せられる問い合わせは、商品やサービスなどに対する質問や意見などさまざまです。
一次対応の自動化により、顧客の要望や意見を聞き取って定型的な問い合わせはその場で回答、オペレーターの対応が必要な内容であれば要件を聴取し、追って担当から折り返し連絡とすることで、オペレータのヒアリングの時間を短縮化することもできます。
自動回答できる幅を徐々に広げていくことで、効率化できる範囲も広げていくことができます。
通信販売などの注文受付におけるあふれ呼対応
通信販売は、CMなどの広告が入ったタイミングで顧客からの注文の入電が多く入ります。
オペレーターの増員対応しても対応しきれない、あふれ呼が発生しやすい状態になり、機会損失が課題となっています。
顧客対応を自動化すると、入電数に応じて同時に数百通話を対応でき、スナッチ対応に切り替えることで、オペレーターが折り返し連絡に専念するといった業務の切り分けが可能です。
さらに、次のステップとして注文受付にも自動化を拡張することも可能です。
これまでの機会損失の解消に一役を担うことで、売上アップの効果があらわれるでしょう。
商品やサービスの24時間365日問い合わせ対応
商品やサービスの問い合わせ対応はどのような顧客の声も拾えるよう、24時間365日対応が理想的です。
なぜなら、商品やサービスの問い合わせは商品やサービスの利用方法や契約手続きなど、業務範囲が幅広いからです。
しかし、予算に限りがあってオペレーターによる24時間対応が困難であるケースや入電数の変動が予測できない状況では、問い合わせ対応時間を限定する必要があります。
顧客応答を自動化することで、オペレーターの勤務時間外に入電があっても問い合わせ内容を確認し、翌日以降回答するといった対応が可能です。
まずは夜間のみ稼働させ、安定稼働が確認できたら土日祝日、さらには平日日中へと拡張していくことも可能です。
美容院や医院の予約受付対応
美容院や医院などの予約が必要な業種においては、顧客からの予約連絡に都度従業員が対応していると、他の業務に支障をきたしてしまう恐れがあります。
予約受付応の自動化においては、顧客からの予約希望内容の聴取、予約内容を確認、予約システムとの自動連携・書き込みなど、自動化範囲が広いため、段階を踏みながら自動化を行い、その都度想定通りにシナリオが稼働していることを確認しながら拡張していくことが成功の秘訣です。
電話応答自動化を導入する際の社内での進め方
電話応答の自動化を導入するためには、計画を策定し手順を踏んで進めていくことが重要になります。
あらかじめ自動化を導入する業務を選定し社内の合意形成方法を決めておくと、スムーズな導入実現が可能です。
ここでは、自動化の検討段階から実際に導入に至るまでの社内での進め方について解説しましょう。
自動化を導入する業務選定
電話応答を自動化するためには、まず自動化する業務の選定が必要です。
自動化する業務は、導入段階では一部の定型化されている業務から始めると効果がでやすいことを前述で挙げています。
また、自動化する業務が決まったら、活用するツールや予算の見積もり、既存システムとの連携の有無など具体的な内容まで検討を重ねましょう。
加えて、自動化する業務で対応するシナリオ(スクリプト・フロー)についても策定していきます。
例えば、病院の診察予約対応の場合、希望する日時を聞き取りして予約システムから空きを確認したのち、予約確保して顧客にその旨を伝えて終話するまでの流れをシナリオとして設定します。
その際に、どのようなトークスクリプトにするのか、どういった内容であればエスカレーション対象としオペレーターに転送するのかなどの具体的な内容まで検討できると導入がイメージしやすいでしょう。
社内の合意形成方法
次に、電話応答自動化の導入について、社内での合意形成を進めていきます。
電話応答自動化を推進する目的や導入イメージ、自動化によって得られる効果などを説明します。
早期に社内で合意を得るためには、説明段階で具体性をもたせることと誰にでもイメージしやすい内容で伝えることが重要です。
説明資料は、導入効果を数値化して自動化を導入するメリットやデメリットを理解してもらったり、イラストなどを用いて自動化する業務をイメージしやすくしたりする工夫を行いましょう。
データ連携やセキュリティリスクのチェック
電話応答自動化の導入が合意形成されたら、導入に向けた準備段階に入りましょう。
まずは、採用する自動化ツールを選定し、既存の電話システムや他のシステムとの連携が問題なくできるかを確認します。
これらの既存システムとの連携ができない場合、導入時に新たにデータ化を進める必要性や、従来の業務フローを大幅に変更する必要性に迫られるなど、導入までに大幅な労力がかかってしまいます。
そのため、システム連携が滞りなく進むかをチェックしましょう。
また、自動化ツール導入においてセキュリティリスクに問題はないかも確認しましょう。
自動化ツールについては、大切な顧客情報を扱うために堅牢なセキュリティが求められ、全ての通信の暗号化やシステム内での各種処理完結などの対応が必要です。
導入を検討しているツールがどのようなセキュリティ対策を行っているのか、あらかじめ確認しておきましょう。
サポートの活用有無
電話応答自動化ツールの導入を円滑に進めていくためには、専門的な知識を要するためサポートを活用すると良いでしょう。
導入段階においては、自動化業務の切り分け、優先度の策定、他システムとの連携など、運用開始までの課題に対応できる体制が求められます。
サポートの内容例としては、ナレッジベースを使った操作疑問点の解消、サポートスタッフによる効果の検証、運用支援などが挙げられます。
自社で全て対応するのはコストや労力面でも困難であるため、サポートをうまく活用するのがおすすめです。ツールベンダーがサポートを行っている場合もあれば、ベンダーのパートナー企業が導入・運用支援を行っているケースもあります。
導入効果測定の目標値設定
最後に、電話応答自動化ツール導入において、効果測定を実施する際に目標値を設定しましょう。
例えば、「応答率を何%アップさせる」、「何割の入電を自動化で対応する」というように、具体的な数値を設定して導入効果を測定します。
目標値の設定においては、自動化ツールを導入する目的に照らして行うことが前提になります。
また、目標値ははじめから高い数値を求めるのではなく、業務範囲の拡張とともに段階的に上昇させると良いでしょう。
電話応対における顧客対応を自動化するならボイスボットがおすすめ
本記事では、電話応対における顧客対応の自動化についてツールの紹介や推進のポイント、具体的な活用例、社内での進め方について紹介しました。
AIによる音声システムや自然言語処理の技術を活用した自動化ツールを活用できると、オペレーターの人員不足やあふれ呼などによる機会損失などの課題解決につながります。
また、顧客対応の自動化は、定型化されている業務など一部導入しやすいところからスタートし、導入効果を測定しながら徐々に対応業務範囲を拡張していくと良いでしょう。
電話応対の自動化ツールは、コールセンターだけでなく、自治体や病院などさまざまなシーンで活用されています。
顧客対応の自動化を進めていくためには、自動化する業務の選定や社内での合意形成など段階的に行い、導入後も効果測定を継続しながらPDCAサイクルを繰り返すことでより効果が得られるようになるでしょう。
電話応対における顧客対応を自動化するなら、AIボイスボット「commubo(コミュボ)」がおすすめです。
顧客対応が音声で完結でき、自然な会話で応答品質の均一化や顧客満足度の向上に一役を担えます。
自社でボイスボットの導入を検討している方は、下記をご覧ください。

commuboラボとは?
AIを活用した業務効率化×顧客満足向上を研究するメディアです。
今まで400社以上に電話応対自動化ソリューションを提供してきたソフトフロントが、自動化の考え方や、ボイスボット活用のコツ、お客様の活用事例、AI活用のトレンドなどをご紹介し、企業の生産性向上だけでなく、その先のお客様の顧客体験(CX)向上に役立つ情報を提供していきます。