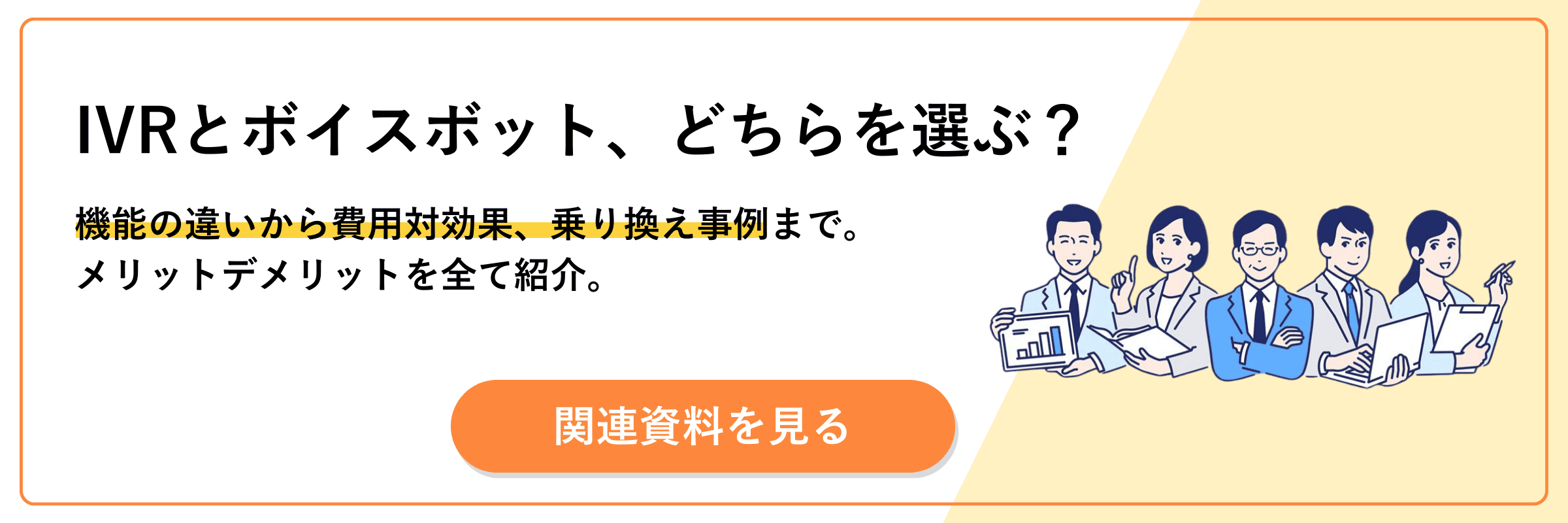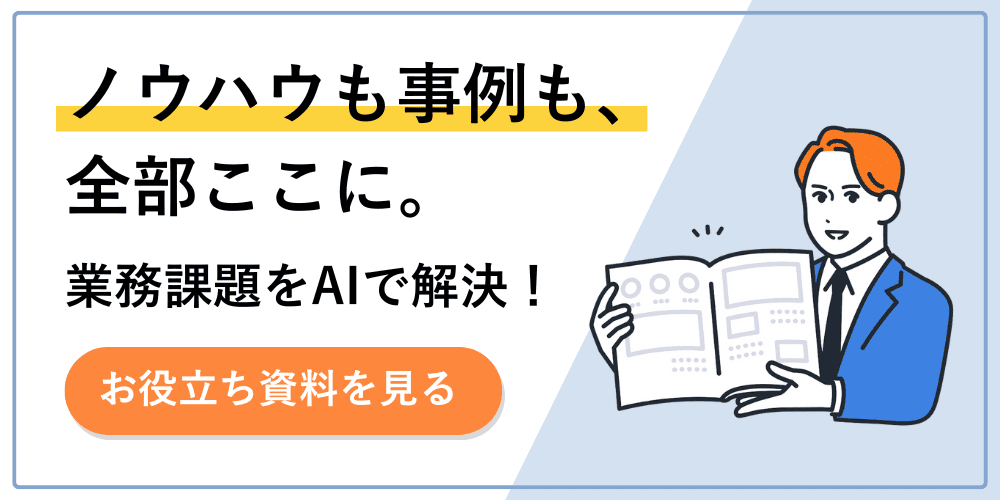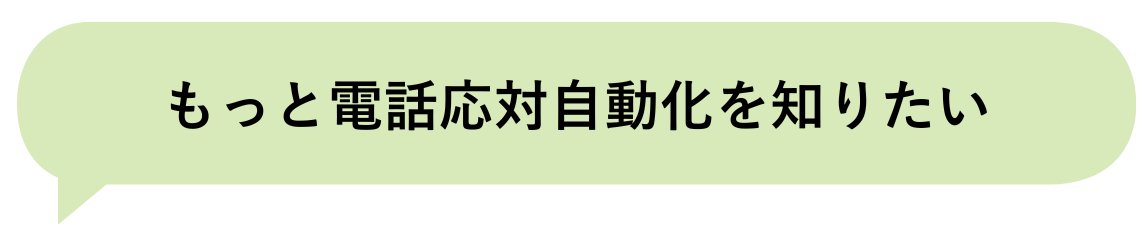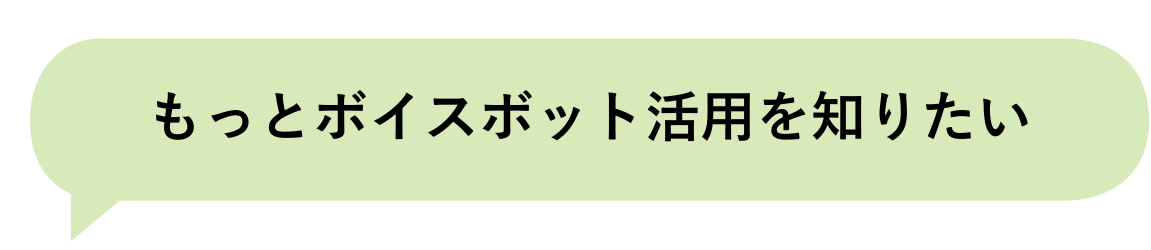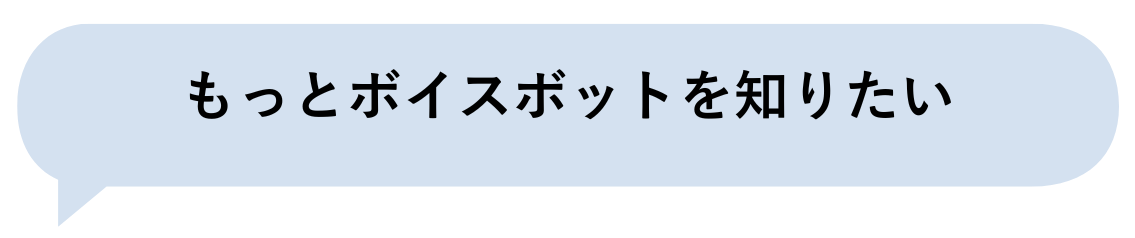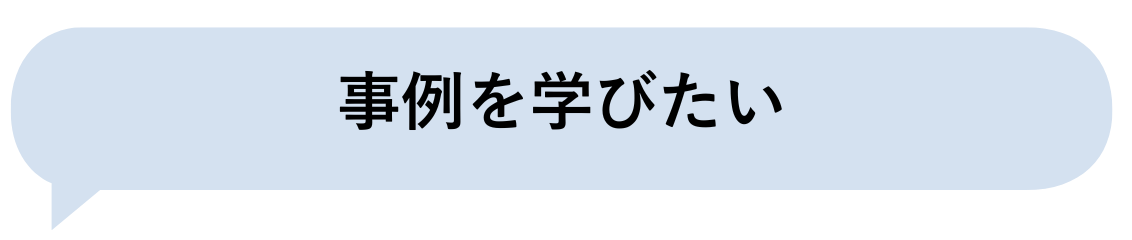AIで解決!コールセンターの人手不足根本原因をデータと事例で解説
作成日:2025年10月1日 更新日:2025年10月1日

「採用をしてもすぐに辞めてしまう…」
「シフトが埋まらず、放棄呼や待ち時間が増えてしまう…」
このように、人手不足が常態化し改善の糸口が見えない状況ではないですか?
実は人手不足は採用強化だけでは解決できない構造的な課題なんです。ここでは、コールセンターの人手不足の原因と影響を整理したうえで、AIも含めた具体的な解決策を5つのポイントで紹介します。
この記事を読めば、少人数でも安定的かつ高品質な対応を実現するための具体的な道筋が明確になり、経営層にも納得感のある改善提案ができるようになります!
新人オペレータの離職率が高い?コールセンターの深刻な現状
コールセンター業界では、特に新人オペレータの離職率が高い傾向にあります。「コールセンター白書2024」の調査によれば、全体の離職率については正規社員と非正規社員を合わせると5%以下が44%、6〜10%が30%となっており、全体としては比較的高い水準ではありません。しかし、新人オペレーターに限ってみると、離職率が21〜30%に達する事業所が18%、さらに31%以上に及ぶ事業所も16%存在しており、他業界と比較すると高い傾向が見られます。
-
離職率が高い背景
この背景には雇用形態ごとのニーズの違いがあります。
コールセンターはアルバイトなど非正規雇用の比率が高い一方で、業務内容は正社員と大きく区別されず、混同されがちです。
そのため、正社員は「キャリア形成につながらない仕事をしている」という不満を抱き、アルバイトは「時給の割に負荷が大きい」と感じて早期離職につながりやすくなります。
このように、正社員・アルバイト双方にミスマッチが生じやすい構造が、コールセンターの高い離職率を招いているのです。
- 正社員=キャリア・処遇軸
- アルバイト=柔軟シフト・短期収入軸
と分けて対策を講じることが重要です。
コールセンターの人手不足は在宅ワークへの流出などが原因
コールセンターの人手不足は以下の理由が考えられます。
- 理由1:在宅ワーク等の柔軟な働き方への流出
- 理由2:クレーム対応などのカスハラによるストレスで離職が起きやすい
- 理由3:給与水準と仕事内容のギャップ
- 理由4:シフト制・夜間対応など労働条件の厳しさ
理由1:在宅ワーク等の柔軟な働き方への流出
コールセンターの人手不足が深刻化する大きな要因の一つは、他職種への人材流出です。
従来は柔軟な働き方ができる点が魅力だったコールセンターですが、近年は在宅ワークやリモート勤務など柔軟な働き方が普及し、人材がコールセンターから離れていく傾向が強まっています。
公的事例集でもテレワークの導入が就業継続や離職抑制に効果的であると報告されており、2015年と比較して特定属性の離職率がほぼ半減した事例も確認されています。
理由2:クレーム対応などのカスハラによるストレスで離職が起きやすい
コールセンターの人手不足の原因の2つ目は、クレーム対応を代表とする感情労働の負担です。
学術研究では、コールセンター業務は感情労働の典型とされ、顧客の怒りや不満を日常的に受け止めることで強いストレスが蓄積しやすいことが指摘されています。特にカスタマーハラスメント(カスハラ)のように、理不尽な要求や攻撃的な言動を受ける場合は、精神的負荷がさらに高まります。
こうした精神的負荷は、適切なサポート体制やケアが不足している場合、短期間での離職につながりやすいでしょう。
理由3:給与水準と仕事内容のギャップ
コールセンターの人手不足の原因の3つ目は、給与水準と仕事内容の乖離です。
採用時の平均時給や条件は地域・センターによって差が大きく、提示条件に期待して入社したものの、実際の業務内容や精神的負担の大きさとの間にギャップを感じるケースが少なくありません。
期待と実態の不一致が早期離職を加速させる場合があります。
理由4:シフト制・夜間対応など労働条件の厳しさ
コールセンターの人手不足の原因の4つ目に、シフト制や夜間対応といった労働条件の厳しさもあげられます。
コール数に応じた人員計画のため、急な休みが取りにくく、生活リズムが崩れやすい勤務環境が続けば、ワークライフバランスに不満を持つ人材は他業種へ転職してしまいます。
24時間対応のコールセンターの構築について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
コールセンターの人手不足がもたらす3つの影響
顧客対応遅延による満足度の低下
コールセンターの人手不足がもたらす影響の1つ目は、顧客満足度の低下です。人員不足はまず顧客対応の遅延に直結し、応答までの待ち時間が長くなると放棄呼が増加します。放棄呼率は一般的に5~8%が目安であり、これを上回ると顧客はつながる前に離脱し、機会損失や不満につながります。
さらに、一次解決率(FCR)は70%以上が望ましいとされますが、人手不足で解決力が低下すると、顧客は「何度もかけ直さなければならない」と感じやすく、不満を強めます。
このように、人手不足は待ち時間の延長から放棄呼を増加させ、結果として顧客満足度を大きく損ない、企業全体の評価にも悪影響を与えるのです。
オペレータ負荷が引き起こすバーンアウト
コールセンターの人手不足がもたらす影響の2つ目は、残存オペレータの負担の増加です。人手不足は残ったオペレータの負担を増大させ、ストレスや離職を加速させる大きな要因です。人員不足が常態化すれば、残存オペレータに業務が集中し、精神的・肉体的負荷が高まります。
特に問題となるのがバーンアウト(燃え尽き症候群)で、これは過度のストレスによって心身のエネルギーが枯渇し、意欲や生産性が著しく低下する状態を指します。このように、人手不足→過重労働→ストレス増加→離職という悪循環が続けば、短期的な改善は困難で、長期的な組織疲弊に直結します。
研修コストの増加
コールセンターの人手不足がもたらす影響の3つ目は、研修コストの増加です。採用から教育、OJTに至るまで時間と費用がかさむ上、対応品質のばらつきに伴う再対応コストまで発生し、企業にとって重大な経営リスクです。
コールセンターは離職率が高いため、断続的な採用と研修が必要となり、教育費が重くのしかかります。新たなスタッフを繰り返し育成する必要があり、教育にかけた費用や時間が水の泡となるケースが後を絶ちません。ある試算では、離職1名あたりのコストは数百万円規模に達することもあるとされます。人手不足は現場に留まらず、顧客体験の質、従業員の働き方、そして経営コストにまで影響が及ぶ重大事態なのです。
コールセンターの人手不足を構造的に解決する5つの方法
コールセンターの人手不足を構造的に解決する方法を5つ紹介します。
- 労働条件の改善
- 業務プロセスの見直しとナレッジの仕組化
- 研修制度・評価制度の整備
- コールセンター代行(BPO)の活用
- AI・自動化ツールの活用(IVR/チャット/ボイスボット)
労働条件の改善
人手不足を解決する方法の1つ目は、労働環境の改善です。人手不足の原因は、リモートワークなど柔軟な働き方への人材流出や厳しいシフト制・ストレスの高い感情労働からの回避でした。
コールセンターにおいても柔軟シフトや短時間勤務、時差出勤を導入することは、家庭や学業と両立を希望する人材の確保につながります。また、在宅勤務やハイブリッド勤務の選択肢を設ければ、通勤負担を軽減し、長期的な就業継続を後押しできます。厚生労働省の事例集でも、テレワークの定着によって離職率がほぼ半減した事例も確認されています。
-
検討したい勤務形態と制度
勤務形態
- 短時間勤務
- 時差出勤
- スタッフ個々の要望に応じたカスタマイズシフト
- 在宅勤務
- ハイブリッド勤務
制度
- リラックスできる休憩室
- 業務終了や休憩への移動に設けたクールダウン動線
- クレーム対応後や新人研修後に管理者が声をかけやすいレイアウト
- メンター制度の導入
柔軟な働き方の仕組みやメンタルケアに配慮した労働環境の改善は、コールセンターの人手不足の解決につながります。
業務プロセスの見直しとナレッジの仕組化
コールセンターの人手不足を解消する方法の2つ目は、業務業務プロセスの見直しとナレッジの仕組化です。
業務を注文対応、解約受付、クレーム対応といった役割別に細分化しましょう。細分化することで、新人採用の段階から適性に応じた配置が可能になり、教育効率も向上します。
FAQやマニュアルのナレッジ化は自己解決を後押しし、問い合わせ件数の削減につながります。
例えば、FAQ導入によって受付件数を50%削減した事例もあり、顧客が自身で解決できる体制を整えることは、オペレータの負担軽減にも大変有効です。
このように、業務フローの精緻な設計とナレッジの仕組み化を組み合わせることで、業務効率・品質・従業員の働き方を包括的に改善できる重要な方策と言えるでしょう。
研修制度・評価制度の整備
人手不足を解決する方法の3つ目は、研修評価制度・評価制度の見直しです。
従業員が評価制度の不透明さやキャリアパスの見えなさを感じると、モチベーションが低下し、離職の要因となりやすいためです。
公正かつ納得性のある人事評価制度を運用した結果、コールセンター業界で異例の年間離職率2.2%を達成した事例もあります。
このように研修や評価制度を見直して透明性を高め、キャリアパスを明確に提示することは、単なる定着支援以上の効果を生み、組織全体の安定性と質を向上させる重要な施策です。
コールセンター代行(BPO)の活用
人手不足を解決する方法の4つ目は、外部委託の活用です。
自社でピーク時対応や営業時間拡張、多言語対応を行おうとすると大きな時間とコストがかかります。一方で、BPOに委託すれば必要に応じた人的リソースとスキルを確保し、短期間で稼働を安定させることができます。
外部委託は人手不足に対するスピーディで柔軟な対応策であり、費用相場も明確で導入しやすい一方、品質基準やKPIの共有・ナレッジ共有の体制を低下させない設計が必要です。
AI・自動化ツールの活用(IVR/チャット/ボイスボット)
人手不足を解決する方法の5つ目は、人手不足解消の本命とされるAIや自動化ツールの導入です。
AI活用によりルーティン業務の自己完結化が進み、オペレータの負担軽減と応答の安定化が期待できます。
中でも注目されているのがボイスボットです。
音声で再配達受付や契約内容の照会、変更対応を自動完結できるため、入電数そのものを削減できます。
例えば不動産業の建物管理問合せでは、一次受付を自動応答化することで工数を約40%削減。メーカーの24時間窓口では、応答率を最大15%改善した事例も報告されています。導入のステップは段階的に進めるのが効果的です。
このようにAIを活用することで、応答率向上・放棄呼減少・顧客満足度改善を同時に実現できる可能性があります。
IVRやボイスボットについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
人手不足の解消には構造改革とツール導入で根本解決
この記事では、コールセンターの人手不足は一時的な採用難だけでなく、構造的な課題であり、これを放置すれば、顧客満足度の低下や現場オペレータの疲弊、さらには採用・研修コストの増大という悪循環を招くことを説明しました。
また、解決のカギは複数の施策を組み合わせて体系的に取り組むことにあることを解説しました。
人事制度や従業員のモチベーション管理をいきなり大きく変えるのは難しいと思います。
一方で、ボイスボットなどのツール導入は、場合によっては大きく業務効率化が可能で、そのことにより、従業員の業務改善・人材定着にもつながります。
ソフトフロントジャパンが提供するAIボイスボット「commubo(コミュボ)」は、聞く・考える・話すの各処理と、自然に会話を続ける機能を一つにまとめて提供する、SaaS型のボイスボットサービスです。
IVRとは異なり、お客様の音声を認識し対応を変化させ、自然な音声で応対することで電話をかけるお客様の「電話がつながらない」を解消します。
ボイスボットについての不明点やお悩みについては、ソフトフロントジャパンへご相談ください。

commuboラボとは?
AIを活用した業務効率化×顧客満足向上を研究するメディアです。
今まで400社以上に電話応対自動化ソリューションを提供してきたソフトフロントが、自動化の考え方や、ボイスボット活用のコツ、お客様の活用事例、AI活用のトレンドなどをご紹介し、企業の生産性向上だけでなく、その先のお客様の顧客体験(CX)向上に役立つ情報を提供していきます。