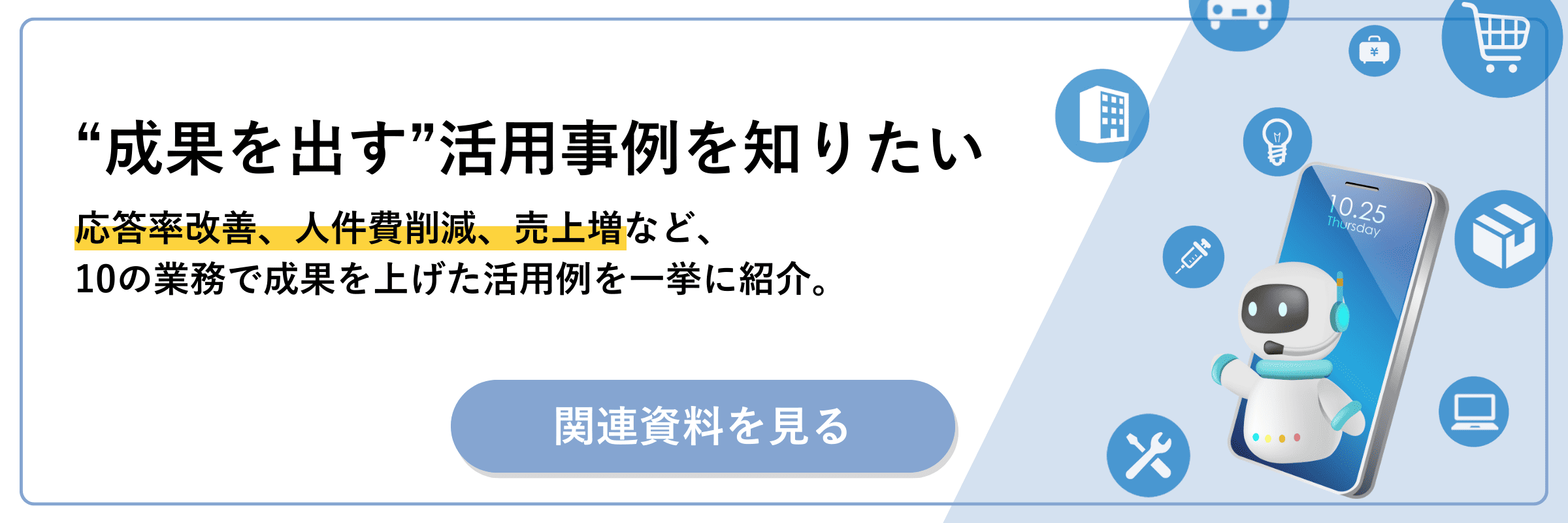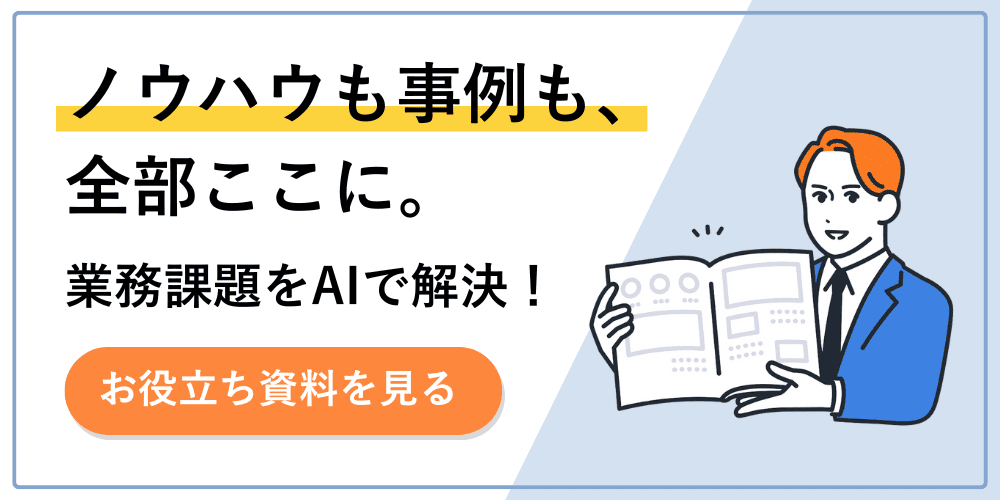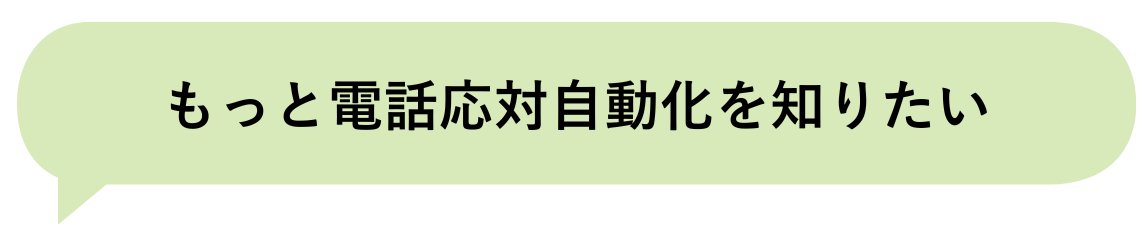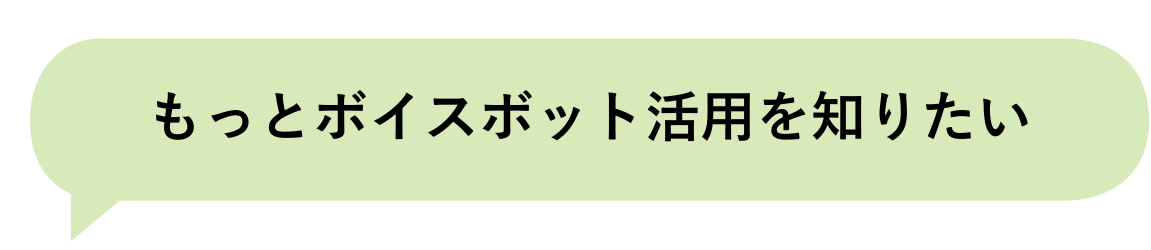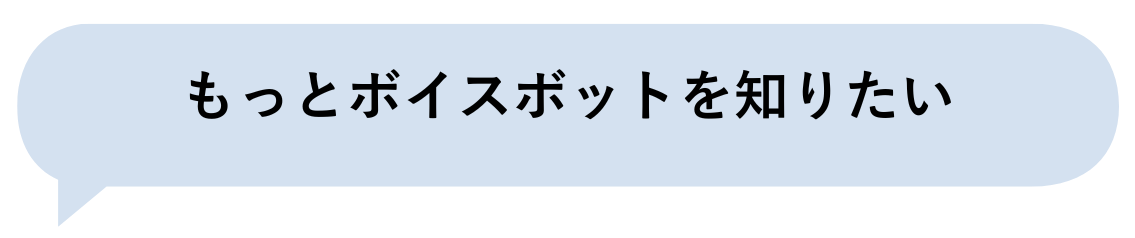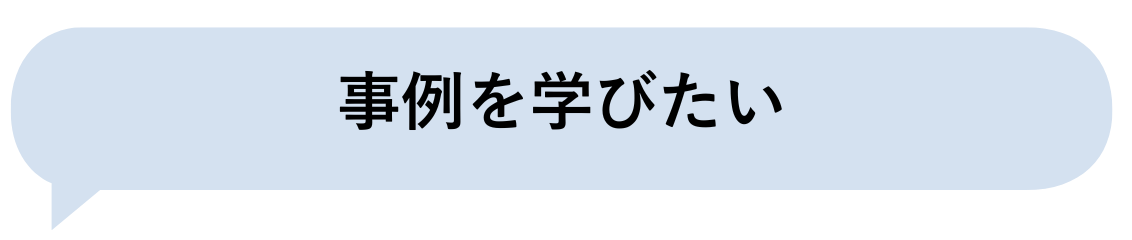ボイスボット導入事例から学ぶ成功のカギと業界別活用シーン
作成日:2025年10月1日 更新日:2025年10月1日

ボイスボットは、音声認識とAIを活用し、顧客との会話を自動化する仕組みです。近年、コールセンターや予約受付、FAQ対応など、さまざまな業務で導入が進んでいます。しかし「実際に何ができるのか?」「どの業務に向いているのか?」と疑問を持つ方も多いはず。本記事では、導入事例をもとに成功のカギを解説し、業界別の活用シーンをご紹介します。ボイスボットの可能性を具体的に理解し、自社導入の判断に役立ててください。
ボイスボットとは?
ボイスボットとは、AI(人工知能)を活用したAI電話自動応答サービスです。AIがユーザーの音声を認識し、適切に応答することで問い合わせ対応や予約受付などの業務を効率化します。
ボイスボットの仕組み
ボイスボットの仕組みは、以下の流れで構成されています。
-
音声認識
ユーザーの声をテキストに変換します。
-
自然言語処理
テキストから意味を理解し、意図を解析します。
-
対話管理
会話の流れを把握し、適切な応答を決定します。
-
音声合成
応答内容を音声に変換し、ユーザーに返します。
この1〜4の一連の処理により、音声での自動応答が可能になります。
ボイスボットの種類
ボイスボットは主に3種類に分類されます。
-
シナリオ型(ルールベース型)
まず「シナリオ型(ルールベース型)」は、あらかじめ設定された対話シナリオに沿って応答する仕組みで、選択肢に応じて分岐する構造が特徴です。
-
AI学習型(自然言語処理型)
次に「AI学習型(自然言語処理型)」は、自然言語処理を活用し、ユーザーの自由な発話を理解して柔軟に応答します。
-
ハイブリッド型(シナリオ+AI学習)
最後に「ハイブリッド型(シナリオ+AI学習)」は、シナリオ型の安定性とAI型の柔軟性を組み合わせたものです。
現在は「1. シナリオ型(ルールベース型)」が主流となっています。
ボイスボットとIVRやチャットボットとの違い
顧客対応を自動化するツールはボイスボットだけではありません。ここではIVRやチャットボットとの違いについて紹介します。
IVRとの違い
IVRとは、電話の音声ガイダンスに従い、電話機のボタンを押して応答するシステムです。ボイスボットとの大きな違いは「IVR=ボタンで応答」「ボイスボット=音声で応答」という点にあります。IVRはシンプルな振り分け対応や、数値情報(電話番号、顧客番号など)の聞き取りに適しています。一方、ボイスボットは固有名詞(製品名、担当者名など)、時間外や担当不在時の伝言などの聞き取りに適しています。
チャットボットとの違い
チャットボットとは、WebサイトやSNS上で顧客とやり取りする際に、テキストを使って会話を自動化するシステムです。ボイスボットとの大きな違いは「チャットボット=テキストでやり取り」「ボイスボット=音声でやり取り」という点にあります。チャットボットはテキストでやり取りするため、騒がしい環境でも利用しやすく、周囲に会話内容を聞かれる心配もありません。さらに、URLや画像といった視覚情報を提示できる点も強みです。一方、ボイスボットは音声でやり取りするため、手がふさがっている状況や、文字入力が苦手な高齢者などにとっても利用しやすいのが強みです。
各ツールの特徴を理解し、目的に応じて使い分けることが重要です。
ボイスボットに向いている4つのシーン
ボイスボットは、定型業務や一次受付、外部システムとの自動連携が必要な業務に最適です。ここではボイスボットに向いているシーンを4つ紹介します。
シーン1:簡単な問い合わせ対応
営業時間、店舗住所、料金、配送状況など、決まった質問に答える簡単な問い合わせ対応は、ボイスボットが最も得意とする領域です。顧客はオペレータを待つことなく即時に情報を得られ、満足度向上につながります。また、定型的な質問を自動で処理できるため、オペレータは複雑な案件対応に集中でき、業務効率化にも大きく貢献します。さらに、24時間対応が可能になるため、顧客にとっても利便性が向上し、企業側にとってもコスト削減と顧客体験の改善を同時に実現できます。
シーン2:代表電話やヘルプデスクの一次受付
代表電話やコールセンターへの着信は、まず担当部署や担当者に適切に振り分けることが重要です。ボイスボットを導入すれば、顧客の要件をヒアリングし、該当部署へスムーズに転送できます。例えば「請求に関する問い合わせ」「製品の故障連絡」など、あらかじめ設定された分類に沿って案内することで、担当者へのつなぎ間違いや対応遅延を防止します。さらに、本人確認や基本情報の取得も自動化できるため、オペレータが通話を開始する時点で必要情報が揃い、対応時間を大幅に短縮できます。
シーン3:本人確認を伴う再発行受付
保険証券や契約書などの書類再発行受付は、本人確認作業を伴うため、外部システムと連携できるボイスボットでの自動対応に非常に適しています。顧客から契約番号や氏名を聞き取り、CRMや基幹システムと連携し、データベースと照合する作業を自動化することで、24時間365日受付が可能になります。また、顧客情報の自動取得や再発行手続きの進行状況確認もでき、オペレータによる手動処理を最小限に抑えられます。これにより、顧客にとってはスピーディな対応が実現し、企業にとっては業務効率化とコスト削減が可能になります。
シーン4:予約・来店受付
飲食店、病院、美容院などの予約や来店受付業務は、ボイスボットとの親和性が高い分野です。希望日時、人数、利用目的など、必要情報を聞き取り、外部の予約管理システムと自動連携することで、人手を介さずに予約完了が可能になります。さらに、予約内容の確認や変更、キャンセルにも対応できるため、営業時間外でも予約を受け付けできます。これにより、顧客はストレスなく希望時間に予約でき、企業側はオペレータを配置するコストを削減しながら、利便性を高めることが可能になります。
ボイスボットに向いていない4つのシーン
ボイスボットは幅広いシーンで活用可能ですが、複雑さやカスタマイズの必要性が伴ったり、感情に寄り添った対応が必要なシーンでは不向きな場合があります。ここではボイスボットに向いていないシーンを4つ紹介します。
シーン1:トラブルシュートや緊急度が高い問い合わせ対応
システム障害や製品不具合など、状況に応じた判断が求められるトラブルシュートは、現状のAI技術では完全な対応が難しい領域です。特に緊急性が高い場合、誤った判断や遅延は大きな損失や顧客離れにつながる可能性があります。こうしたケースでは、顧客の不安を受け止めながら柔軟な判断を下せる人間のオペレータが不可欠です。ボイスボットは一次受付で内容を整理し、オペレータへの迅速な引き継ぎをする補助的な役割での活用が望ましいでしょう。
シーン2:旅行プランのコンシェルジュやテレアポ対応
旅行プランの提案やテレアポのような営業活動は、顧客とのコミュニケーションの中でニーズを深く理解し、最適な提案をするスキルが求められます。特に、顧客の感情やトーンを読み取り、相手の興味を引き出す柔軟性が必要なため、自動応答だけでは十分な対応ができません。また、相手の予算や好みに応じて複数の選択肢を提示する場合も、細かなニュアンスを理解する人間による対応が適しています。
シーン3:カウンセリングやお悩み相談
メンタルケアやカウンセリングなどの分野では、相手の感情に寄り添う姿勢と信頼関係の構築が重要です。AIは一定の共感表現を模倣できますが、実際の感情を汲み取る力には限界があります。不適切な応答は、顧客の不信感や不安感を増幅させる恐れがあります。そのため、カウンセリングや相談業務は、専門知識と人間らしい配慮を持つオペレータやカウンセラーによる対応が不可欠です。
シーン4:クレーム対応
クレーム対応では、顧客の怒りや不満を正しく理解し、適切な言葉や態度で対応する必要があり、ボイスボットが臨機応変な謝罪や提案をすることは困難です。誤った対応や定型的な返答は、顧客の不満をさらに悪化させる可能性があるため、信頼関係を重視するこの領域は人間の判断が求められます。ボイスボットは、オペレータにつなぐ前に基本情報を取得する一次対応としての役割にとどめるのが望ましいでしょう。
ボイスボット活用例・導入事例3選
ここではボイスボットを活用した導入事例を3つ紹介します。
事例1【通販】注文受付 あふれ呼対応:スナッチ対応で大量注文をさばき売上増を実現
-
業務課題
通販事業を展開する企業さまでは、営業時間外の入電が殺到し、呼損が多発していました。その結果、注文の機会損失が発生し、発注生産性の伸び悩みが大きな課題となっていました。さらに、導入していたIVRもプッシュボタンに移行できない高齢者が多く、完了率は60%と伸び悩んでいました。
-
ボイスボット導入後
営業時間外の入電に対してボイスボットがスナッチ対応を実施。一次受付のみを自動化することで応対時間を極力減らし、大量注文をさばきました。その後、一両日中にオペレータがコールバックして受注に専念するハイブリッド体制を構築しました。
-
導入効果
あふれ呼対応により完了率は94%を達成し、IVR時代の課題を大きく改善。ボイスボットとオペレータの対応時間を分け、効率的なハイブリッド応対体制で受注率の向上を実現しました。
事例2【クレジットカード】本人確認含む問合せ対応:24時間自動応対でクレームレス環境へ
-
業務課題
多くのクレジットカード会員を抱える企業さまでは、問い合わせ窓口へのクレーム電話が多く、担当者が疲弊。さらに、時間外窓口がなく、顧客満足度の低下も顕著でした。IVRの導入を検討されましたが、ボタンプッシュ式ではお客様の氏名の聞き取りに対応できず、最適な対応策を見つけるのにお困りでした。
-
ボイスボット導入後
利用料金の引き落とし確認などの定型的な問い合わせはボイスボットが24時間対応し、営業時間外の電話も自動で受け付ける体制を整備しました。さらに、会員情報をシステムと連携することで、ボイスボットが本人確認後に問い合わせ内容に回答できる仕組みを整えました。引き落とし情報は、音声案内後に会員様個人のスマートフォンへSMSで自動送信する仕組みを構築しました。
-
導入効果
結果として、定型業務にかかっていた担当者の対応時間を削減し、業務効率化を実現。ボイスボットが応対することで、クレーム発生も皆無となり、大きな効果を得られました。また、音声認識のチューニングによって、カード会員様の名字の聞き取り精度が約90%に向上しました。クレームのほとんどは「人」に対する行為とされるため、人格の無い「AI」が対応することで、心理的ストレスを回避する副次的な効果を発揮しました。
事例3【金融/保険】初期督促コール:入金案内を完全自動化しつつ、入金率を維持
-
業務課題
金融・保険業界の企業さまでは、初期督促業務に多くの課題を抱えていました。従来はオペレータによる手動架電のため、業務遂行が勤務シフトに依存していました。また、架電業務の負担が大きく、相手が不在の場合には鳴り戻り対応が発生し、結果的に業務効率が低下。さらに、架電と鳴り戻りの両方の応対管理に時間がかかる状況が発生していました。
-
ボイスボット導入後
初期督促の架電はボイスボットが担当し、架電リストを元に一斉かつ連続的に自動発信する仕組みを構築しました。さらに、架電状況やトーク内容からステータスを自動入力し、業務効率化を図りました。また、振込先情報を会話で案内せず、SMS送信を使うことで終話までの会話時間を短縮しました。
-
導入効果
その結果、入金率は84%と、人間による架電と同等水準を維持。一方で、人間による架電が不要となり、業務効率が大幅に改善されました。
また、「督促」は架電する側・される側の双方に大きな心理的ストレスがかかる業務です。ボイスボットによる自動督促コールは、架電する側のストレスを軽減するだけでなく、される側にとっても人間とやり取りする場合より、ストレスが少なく落ち着いて対応できるという特徴があります。
-
【まとめ】
ボイスボットは、音声認識とAIを活用して顧客対応を自動化し、業務効率化や顧客満足度向上に貢献します。ただし、すべての業務に適しているわけではなく、定型的な問い合わせや一次受付、予約業務などに強みを発揮します。導入を成功させるには、目的や運用体制に合わせた設計が不可欠です。そのためには、豊富な実績とノウハウを持つサービスを選ぶことが重要です。
ボイスボットの導入なら、契約継続率98.1%のAIボイスボット「commubo(コミュボ)」がおすすめです。多様な業界で培ったノウハウをもとに、スムーズな導入と高い顧客満足度を実現します。

commuboラボとは?
AIを活用した業務効率化×顧客満足向上を研究するメディアです。
今まで400社以上に電話応対自動化ソリューションを提供してきたソフトフロントが、自動化の考え方や、ボイスボット活用のコツ、お客様の活用事例、AI活用のトレンドなどをご紹介し、企業の生産性向上だけでなく、その先のお客様の顧客体験(CX)向上に役立つ情報を提供していきます。