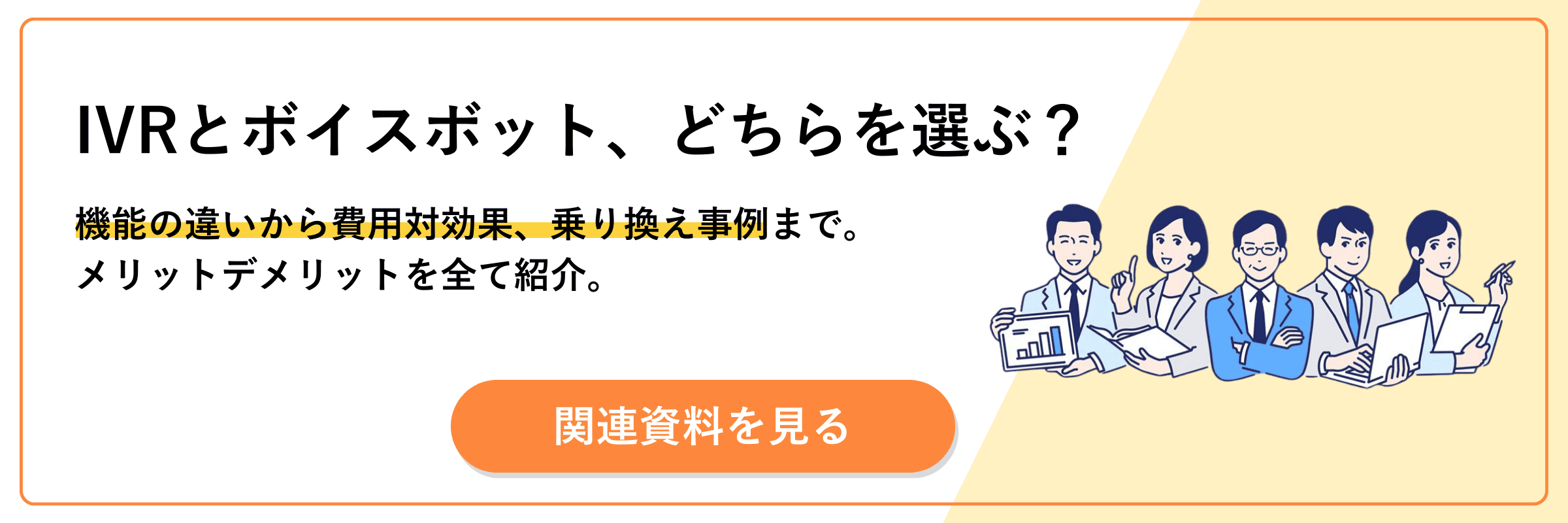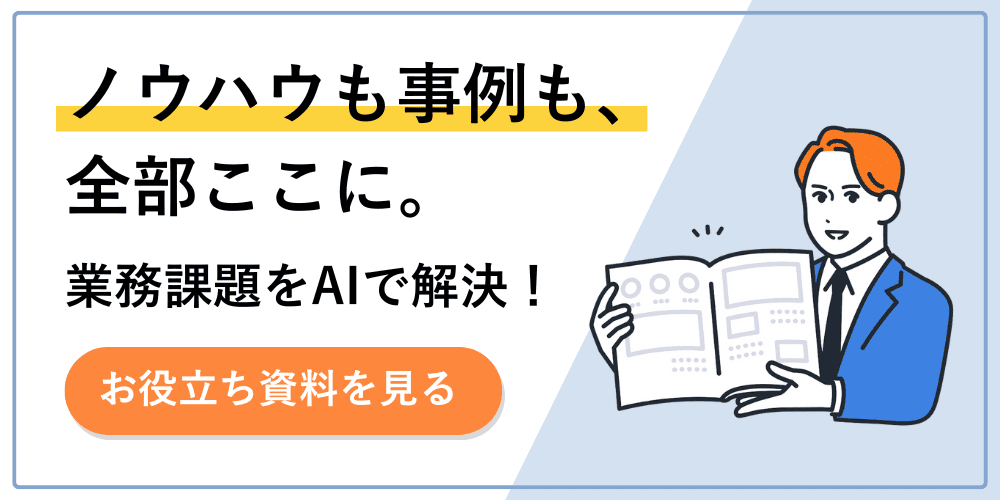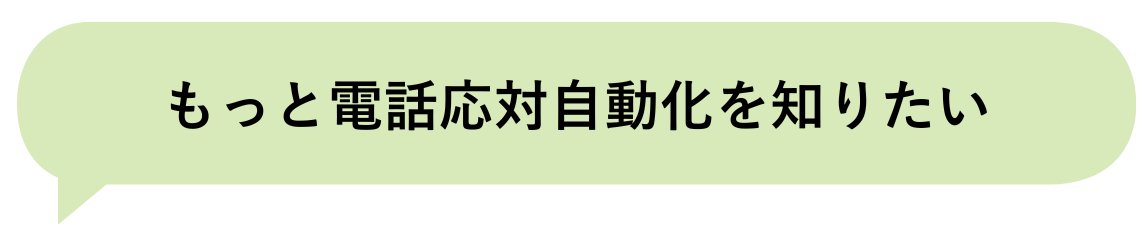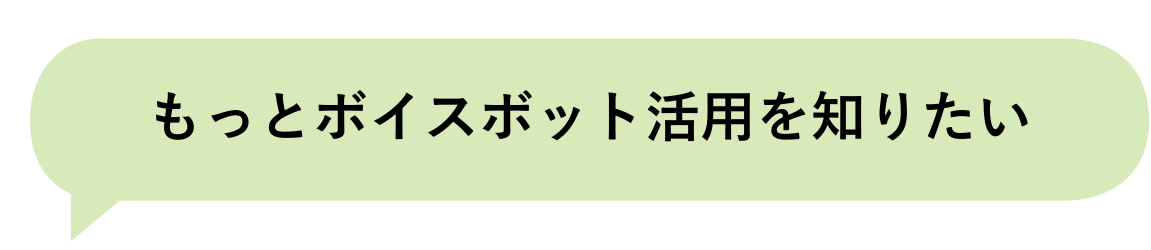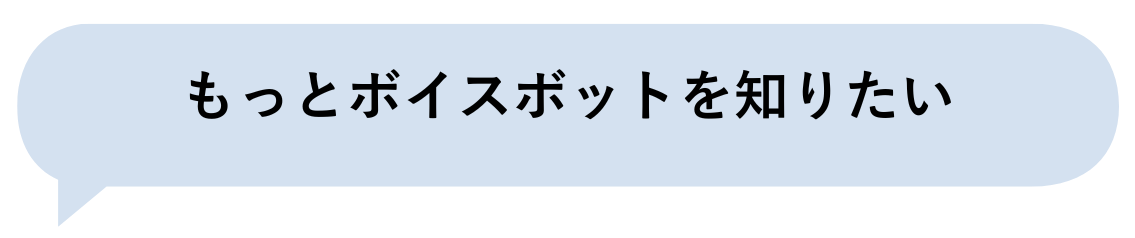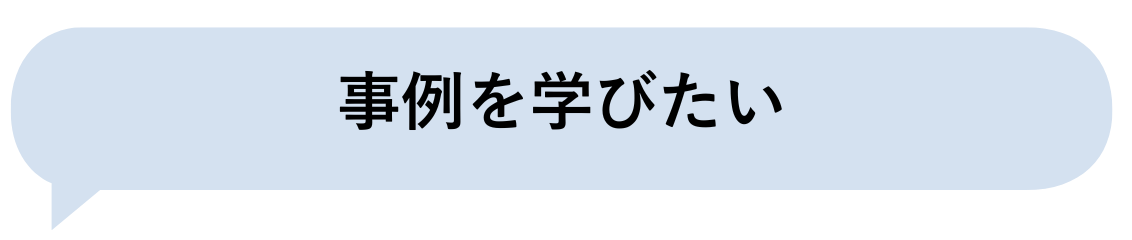コールセンターの離職率が高い理由とは?原因と対策法も紹介
作成日:2025年10月1日 更新日:2025年10月1日

コールセンターは離職率が高い業種といわれており、令和5年の雇用労働調査では全職員の約23%が離職しています。
離職率が高い理由には業務の複雑化や慢性的な人材不足、賃金の低さなどが挙げられます。では、コールセンターの離職対策としてどのような方法があるのでしょうか。
本記事では、コールセンターの離職率が高い理由から原因と対策法について紹介します。コールセンターの離職する原因を知りたい方や、具体的な離職対策を知りたい方はぜひ参考にしてください。
コールセンターは高い離職率
コールセンターは離職率が平均値よりも高く、人材確保ができない点が大きな課題に挙げられています。
現状コールセンターの離職率はどのくらいなのでしょうか。
また、コールセンター別でみても離職率に違いはあるのでしょうか。
厚生労働省の雇用労働調査やコールセンター白書を参考に詳しくみていきましょう。
コールセンターの離職率は23.1%
厚生労働省の令和5年雇用労働調査によると、コールセンターの離職率は23.1%です。
入職率が22.5%なので、コールセンターの離職率が入職率を上回っており、働き手は減少していることが分かります。
一方で、コールセンター市場は新型コロナ禍以降も前年比5%増で拡大を続けており、今後も業務量は増加していく見込みです。
また、業務効率化ツールの導入や呼量予測によるリソース最適化などで生産性アップが図られるものの、放棄呼率は横ばいに推移していることから機会損失が生まれています。
よって、コールセンターの離職率を減少することは喫緊の課題であるといえるでしょう。
離職率について詳しくみてみると、一般労働者では19.3%、パートタイム労働者では32.7%と短時間勤務者の方が離職しやすい特徴があります。
そのため、コールセンターでは正社員かパートタイム採用かによって離職へのハードルに差があると考えられます。
業種別では離職率ベスト3入り
令和5年雇用労働調査について業種別でみていくと、コールセンターは離職率がベスト3に入っています。
コールセンターの離職率は上位である生活関連サービス業・娯楽業や宿泊業・飲食サービス業とともに、離職率が2割以上となっています。
その他の業種は10〜15%程度で推移していることから、コールセンターの離職率は高いことが分かります。
また、産業合計の離職率の平均値が15.4%という点からみても、離職率が高いことは明確です。
離職率20%以上のコールセンターが3割も
コールセンターの離職率についてコールセンター白書によると、コールセンターの中でも、離職率20%以上の企業が3割ほどにのぼります。
また、過去1年以内に採用したオペレーターの離職率に焦点を充てると、離職率20%超の企業が46%と上昇しています。
このことから、コールセンターの離職率は新人オペレーターの離職が多いことが課題といえるでしょう。
コールセンターの離職率が高い理由6つ
コールセンターの離職率が高い理由として、顧客対応の複雑さやクレーム対応、職場での人間関係の不和などさまざまな理由が考えられます。
これらの理由から、コールセンターの労働環境は慢性的にストレスフルになりやすい状況ともいえるでしょう。
ここでは、コールセンターの離職率が高い理由6つについて詳しくみていきましょう。
クレーム対応が多い
コールセンターの離職率が高い理由に、クレーム対応が多い点が挙げられます。
コールセンターでは、顧客へ発信するアウトバウンドと顧客からの電話を受話するインバウンドコールがあります。
インバウンドコールでは、商品やサービスの問い合わせ・申込、使用方法の相談、クレーム対応など多岐にわたります。
クレーム対応は商品やサービスに対する苦情や不具合への対応になりますが、自身が攻められていると感じてしまいがちです。
また、クレーム対応の時間が長時間・長期間にわたり続くと、精神的に大きな負担となってしまうでしょう。
クレーム対応が続く状況が常態化してしまうと、離職につながりやすいといえます。
商品・サービス内容が複雑である
コールセンターで取り扱っている商品・サービス内容が複雑であると、オペレーターが習得する知識量を超えてしまい、対応が難しくなってしまう点も離職率が高い理由です。
特にITや通信分野では、頻繁に商品・サービスのアップデートが行われるため、常に商品・サービス内容を習得していかなければなりません。
また、顧客ごとにカスタマイズされるような商品・サービスになると、より専門的な知識の習得が求められます。
新人オペレーターにとっては習得する知識が膨大であり、対応しきれなくなってしまうケースもみられるでしょう。
その際に、フォローアップしてもらえる体制が整っていなければ、長く働き続けることは困難です。
複雑な商品・サービス内容に対応しうるフォローアップ体制や研修制度の確立が重要といえるでしょう。
給与が低い
コールセンターでは、パートタイム労働者の割合が多い業種の一つです。
パートタイムでは時給制を導入しているケースが多く、長時間勤務していても時給が安いため、給与が低いです。
また、派遣社員や契約社員などであれば、雇用期間が決まっていたり、給与が正社員と比較して低賃金になります。
長時間勤務してかつ業務が多忙である点や、クレーム対応などで精神的に負担が大きい業務にも関わらず給与に反映されないと、モチベーションを保つのは難しいでしょう。
職場の人間関係がうまくいかない
職場内の人間関係がうまくいかないと円滑に業務を進めていくことが困難になり、離職しやすくなります。
他のオペレーターや上司との関係がうまくいかないと、コミュニケーションがうまくとれず、業務に支障が出る可能性が高くなります。
また、コールセンターは常にオフィス内で勤務する環境です。
苦手な人とも同じフロアで働かなければならない労働環境も離職につながりやすいといえるでしょう。
業務が多忙である
コールセンターは慢性的な人材不足によりオペレーター1人にかかる業務負担が大きいため、多忙である状況も離職率が高い理由です。
コールセンターの業務は多岐にわたるうえ、商品やサービス内容が頻繁に更新される場合は常に新たな知識を身につけなければなりません。
また、新人オペレーターが入社してある程度知識やスキルが身につくまで、SVはフォローに入ったり、研修に時間を割いたりする必要があります。
オペレーターのスキルが向上すると、効率よく業務が遂行できます。
しかし、離職率が高いとスキルが身につく前に辞めてしまうので、業務が滞りやすくなり、各オペレーターにかかる負担が大きくなるでしょう。
周囲で離職する人が多い
同じ部署や部門で離職する人が多いと、コールセンターを辞めるハードルが低くなるため、より離職者が増える可能性が高いでしょう。
離職するということは次の就職先を探したり、自分の業務を引き継いだりと大変なことが多いです。
そのため、相応な理由がなければなかなか退職に踏み切れないでしょう。
しかし、周囲で離職する人が頻繁にいると、業務負担や不満に感じることがあれば退職を選択する方が増えます。
離職率の高い職場は退職しやすい雰囲気が高まり、次々に退職者が出るという悪循環が発生している状況です。
このように、コールセンターの離職率が高い原因は、商品・サービス内容が複雑であったりクレーム対応に時間が割かれてしまうなど業務が多岐にわたり、多忙な点などが挙げられます。
また、給与が低い・職場の人間関係がうまくいかないといった業務外の原因も離職につながりやすいでしょう。
慢性的にストレスフルになりやすい状況から離職する人が増え、離職へのハードルが低いのも原因といえます。
コールセンターの離職率に直結するクレーム対応の原因とは
離職率が高まる理由の一つである「クレーム対応が多い」とオペレーターの精神的ストレスが増幅し、離職につながりやすいです。
クレーム対応に発展する原因としては下記の5つが考えられます。
- 架電に対しすぐ受話できない
- 顧客の質問にスムーズに回答できない
- オペレーターのスキルが不足している
- 顧客の依頼に対応できていない
- カスハラ対策ができていない
それぞれの原因について詳しくみていきましょう。
架電に対しすぐ受話できない
顧客が問い合わせなどでコールセンターに架電してもすぐにつながらない状況が続くと、クレームの原因になりやすいです。
架電に対してすぐ受話できない状況は、オペレーター不足や1件あたりの対応時間が長いなどが挙げられます。
離職率が高いコールセンターでは常に人材不足の状態なので、架電数に対応できていないです。
また、架電に対して対応する時間が長くなると、後から架電した顧客の待ち時間も長くなってしまいます。
顧客にとっても架電しても待たされてしまう、何度架電してもつながらないと問い合わせや申込ができないため、不満となり、クレームとなってしまうでしょう。
顧客の質問にスムーズに回答できない
商品やサービスについての問い合わせに対し、オペレーターがスムーズに回答できないとクレームにつながるケースもあります。
コールセンターで問い合わせされる商品・サービスが複雑であったり、頻繁に更新されたりするとオペレーターも多くの知識を身につけなければなりません。
また、オペレーターの経験が浅いとスキルも身についていないため、問い合わせに対し回答を得るまで時間を要してしまうこともあるでしょう。
顧客はコールセンターに問い合わせるとスムーズに回答が得られると考えているので、満足できる回答が得られない場合はクレームにつながりやすいといえるでしょう。
オペレーターのスキルが不足している
オペレーターのスキルが不足していると、顧客とのコミュニケーションがうまくできず、クレームになることがあります。
オペレーターに求められるスキルとは、コミュニケーション能力が根本にあります。
電話でのコミュニケーションは、相手の表情が見えないため、話をよく聞き相手の状況や意図を汲み取る傾聴力や相手に対し正確でかつ親切に内容を伝える言葉遣いなどが必要です。
そのため、相手の年齢層や話すスピードなどから、相手がやり取りしやすい声のトーン、スピードなどにも配慮するスキルも必要です。
これらのスキルが習熟していないと、クレームが発生する可能性が高くなるでしょう。
顧客の依頼に対応できていない
顧客の申込などの依頼に対応できていないと、クレームになる可能性が高いでしょう。
コールセンターへの問い合わせの中には商品・サービスの申込や解約などの依頼も含まれます。
顧客が依頼した内容に対し、オペレーターは正確に処理を行わなければなりません。
しかし、業務が多忙であったり処理が漏れてしまったりして、長期間未処理のままになると顧客が申し込んだ商品・サービスが利用できない状態になります。
また、解約依頼であれば本来不要な利用料などが支払われるといったトラブルに発展します。
カスハラ対策ができていない
コールセンターでカスハラ対策ができていないと、クレーム対応が深刻化する可能性があります。
クレームの中には、カスタマーハラスメント(以下カスハラ)が含まれています。
カスハラとは、厚生労働省によると顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるものです。
具体的には、過剰な請求を行ったり、商品・サービスに不当な言いがかりをつけたりするなどが挙げられます。
近年はコールセンターでもカスハラ対策のマニュアル化が推進され、カスハラへの対応研修を実施するところも増えてきています。
カスハラ対策ができていないと、長時間にわたりオペレーターが対応に追われ、よりカスハラ行為が深刻化するでしょう。
コールセンターの離職につながりやすいクレーム対応はオペレーターの負担が大きい業務の一つです。
クレーム対応が発生する原因はオペレーター不足やスキル不足など顧客にスムーズに対応できない状態が挙げられます。
クレーム対応が多いコールセンターでは離職する人が多く、人材が定着しないことから負のスパイラルに陥っている状態です。
カスハラが発生した際のマニュアル体制ができていないことも原因といえるでしょう。
コールセンターの離職対策方法5つ
コールセンターが高い離職率を改善するためには、人材の定着化と業務の効率化が必要です。
具体的な離職対策として研修制度の構築や採用制度の見直し、AIや自動化ツールの活用などが挙げられます。
離職対策方法の具体例についてどのような効果が得られるのかという点にもふれながらみていきましょう。
オペレーターがスキルアップする研修制度
コールセンターの離職対策として、オペレーターがスキルアップする研修制度の構築により人材を育成します。
新人オペレーターが1年以内に離職する理由としては、業務に必要なスキルが習熟していない状況で携わることで顧客の応対に対する不安が大きいと考えられます。
各オペレーターがどの程度のスキルを身につけていて、今後キャリアを築いていくためにスキルアップできる研修制度を階層別に設けることが重要です。
研修制度の充実は業務の効率化だけでなく、人材が定着し、成果が上がる状況を生み出せます。
キャリア構築できる評価制度
コールセンターの業務は単調なものが多く、キャリア形成を意識しにくい業種といわれています。
評価制度を年単位・月単位といった期間を設けて実施し、定量評価だけでなく定性評価も行うことで、必要なスキルや今後のキャリアが明確になります。
そのためには、各オペレーターとの面談の場を設けて、本人の意向や方向性を共有した上で適切な目標設定から評価まで行いましょう。
そして、今後のキャリア構築が明確になると業務への携わり方が変わり、働きがいやモチベーションにもつながります。
正社員採用と高い給与水準
コールセンターでは派遣社員やパートといった非常勤雇用の採用が多く、負担が大きい業種です。
非常勤雇用は給与水準が低く、雇用期間に限りがあるため、モチベーションを保つのが難しいでしょう。
離職対策としては、正社員として採用することが効果的です。
正社員で採用すると給与水準が向上し、無期限で働き続けられるため、キャリアを構築しやすい状況になります。
また、リフレッシュスペースの設置やセンター内に保育所を設けるなど福利厚生が充実していると未然に離職を防げるでしょう。
カスハラ対策のマニュアル構築
カスハラ対策のマニュアル構築
近年増えているカスハラへの対策マニュアルを構築することでオペレーターの精神的な負担を軽減し、離職対策に効果的です。
厚生労働省で提示しているカスハラ対策は、カスハラの行為別に下記の対策方法を例示しています。
- 長時間電話を続ける時間拘束型…これ以上対応できない旨を伝え、終話する。何度もかかってくる場合は対応可能な時間をあらかじめ伝えて対応する。
- 理不尽な要求を何度も繰り返すリピート型…不合理な要求を続ける場合は対応できない旨を伝え、リスト化して通話を記録し、窓口を一本化する。
- 侮辱的発言、暴言を繰り返す暴言型…名誉毀損や侮辱的発言を繰り返す場合は事実確認できるよう録音し、状況によっては弁護士や警察に相談する。
- 脅迫的な発言・ブランドイメージを下げる発言をする威嚇・脅迫型…複数名で対応し、状況によっては弁護士や警察へ相談する。
- 正当な理由なく特別扱いを要求する権威型…不用意な発言をせず、上席に対応を交換し、要求には応じない。
- SNS/インターネット上での誹謗中傷型…誹謗中傷が掲載されているHPの運営者に削除を求める。損害賠償を求める場合は弁護士などに相談し、適切な対応を行う。
具体的には、カスハラ行為と判断した場合に電話対応時間をあらかじめ決めておき、通話内容を録音します。
状況が変わらない場合は対応者や時間を変更するなどの対応をとり、ひどい場合は弁護士や警察と連携をとりましょう。
これらの一連の対応をマニュアル化しておくことで、オペレーターの精神的な負担の緩和につながります。
AIや自動化ツールの活用
コールセンターの離職対策に、AIや自動化ツールの活用は効果があります。
慢性的に人材不足であるコールセンターでは、顧客が問い合わせてからコールセンターにつながるまでの時間が重要で、問い合わせ内容を正確にデータ化する必要があります。
コールセンターで導入できるAIや自動化ツールとしては、チャットボット・AI自動応答・声紋認証・FAQシステム・AI検索システム・音声認証ツールなどが挙げられます。
業務の効率化だけでなく、一貫した品質のサービスを提供することでCSの向上にもつながるでしょう。
AIや自動化ツールの導入による効果とは
コールセンターの離職対策であるAIや自動化ツールを導入する企業は増えています。
コールセンターで活用できるAIや自動化ツールの種類はチャットボットをはじめ、AI自動応答やテキストマイニング・VoC分析ツールなど多彩です。
ここでは、AIや自動化ツールの導入による効果を、メリット・デメリットにもふれながらみていきましょう。
そもそもAIや自動化ツールとは
そもそもAIツールとは、人工知能技術を活用してさまざまなタスクの補助を行うツールで、データ分析やテキスト生成などが挙げられます。
また、自動化ツールは定型的な業務を機械化することで、自動的に業務を行うツールを指します。
自動化ツールの具体例として、IVRやチャットボット・ボイスボットなどです。
コールセンターの業務にAIや自動化ツールの導入は相性がよいといわれています。
AIや自動化ツールの導入によるメリット
コールセンターでAIや自動化ツールを導入するメリットは下記のとおりです。
- 業務の効率化ができる
- 人手不足を解消できる
- 人件費の削減などコストカットできる
- 24時間いつでも対応できる
- 安定した応対を保てる
- 自動化でできた時間で研修を実施できる
入電に対し一次受付をAIや自動化ツールに切り替えるなど、業務の一部分をAIや自動化ツールが担うことで必要人員を抑制できるため、人手不足や人件費の削減に効果があります。
自動化はオペレーターにとっても業務量が軽減され、スキルアップのための研修などに時間を充てることが可能になります。
オペレーターのスキルアップは応答品質や顧客満足度の向上にもつながり、生産性や売り上げにも影響を及ぼすでしょう
このように、AIや自動化ツールの活用により離職の原因を解消できるだけでなく、コールセンターの業績向上にも一役を担える手法として導入する企業が増えています。
AIや自動化ツールの導入によるデメリット
反対に、AIや自動化ツールの導入によるデメリットは、下記のとおりです。
- 効果的なツールを見出すまで見直しが必要である
- 導入や運用にコストが発生する
- AIに正しい学習を行う機会が必要である
- ハルシネーションを起こす可能性がある
AIや自動化ツールはさまざまあり、どのツールが効果的なのかは導入時点での検討や導入後の効果検証を繰り返し行う必要があります。
また、AIにコールセンターが意図する内容を学習する機会を与え、正確に回答できるよう繰り返し学習させるため、機会が少ないと想定する回答ができないこともあるでしょう。
加えて、ハルシネーションというAIが事実に基づかない回答を生成する現象を引き起こす可能性があり、場合によっては企業の信頼性にも影響を及ぼすこともあります。
これらのデメリットも加味したうえで、AIや自動化ツールの導入を検討しましょう。
AIや自動化ツールの導入が効率化とコストカットにつながる
AIや自動化ツールの導入はコールセンターの業務の効率化とコストカットにつながるツールとして、注目されています。
コールセンターの業務の一部に導入することで、顧客が発信してから受話するまでの時間短縮やオペレーターのスキル差解消で顧客満足度が向上などが期待できます。
また、AIや自動化ツールの導入でオペレーター数を減らすことも可能であり、人件費削減によりコストカットができるケースもあります。
ただし、AIや自動化ツールは導入時にはイニシャルコストのほか、運用時にもランニングコストがかかるため、予算とのすり合わせが重要です。
コールセンターの離職対策ならAIボイスボットのコミュボがおすすめ
本記事では、コールセンターの離職率の現状と離職の原因、離職対策について紹介しました。
コールセンターの離職対策にAIや自動化ツールの導入が効果的で、業務の効率化やオペレーターの負担軽減などメリットが多くあります。
コールセンターで活用できるAIや自動化ツールはさまざまですが、ボイスボットは音声認識技術を使用して顧客と音声で対話し、自動応答を行うシステムとして近年導入する企業が増加しています。
ボイスボットの導入を検討しているのなら、自然な会話で高い業務完了率を誇り、専門知識不要でも自在にカスタマイズできるAIボイスボット「commubo(コミュボ)」がおすすめです。
コミュボは現在使用している電話システムに接続して組み入れできるので、導入コストを大幅にカットできます。
また、 API を通じてさまざまなアプリケーションに会話機能を提供でき、既存システムと相互に連携できるので、業務フローを変えずに導入できるメリットもあります。
AIボイスボットのコミュボについて、詳しく知りたい方はぜひ問い合わせてみてください。

commuboラボとは?
AIを活用した業務効率化×顧客満足向上を研究するメディアです。
今まで400社以上に電話応対自動化ソリューションを提供してきたソフトフロントが、自動化の考え方や、ボイスボット活用のコツ、お客様の活用事例、AI活用のトレンドなどをご紹介し、企業の生産性向上だけでなく、その先のお客様の顧客体験(CX)向上に役立つ情報を提供していきます。