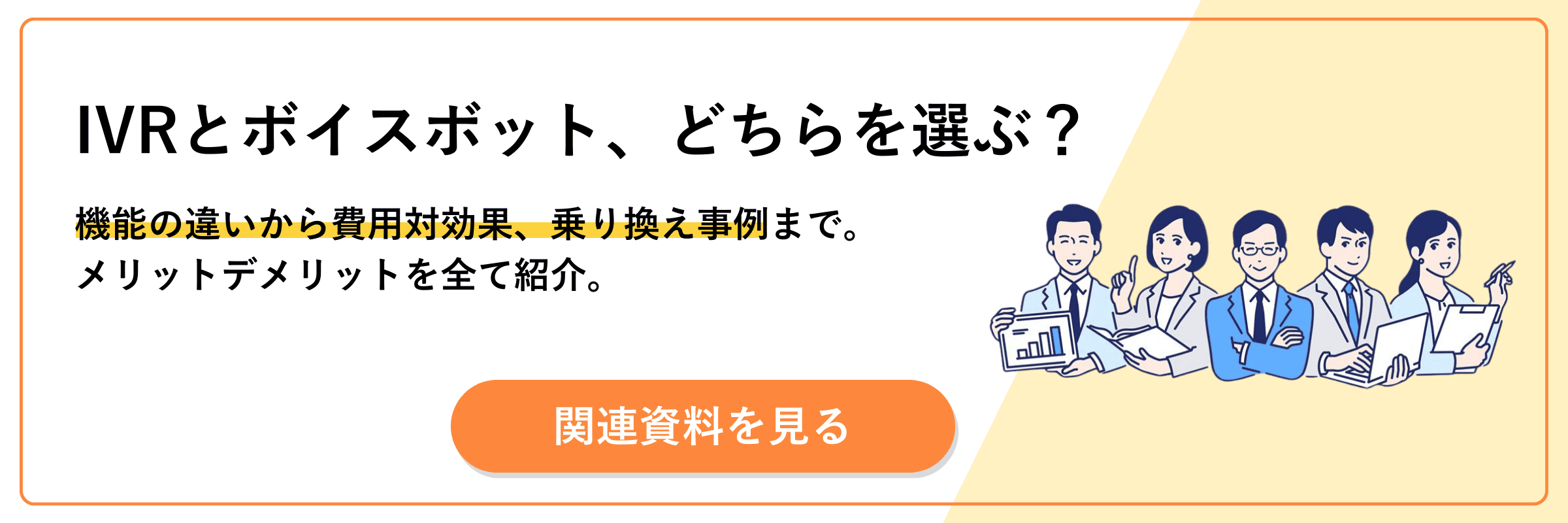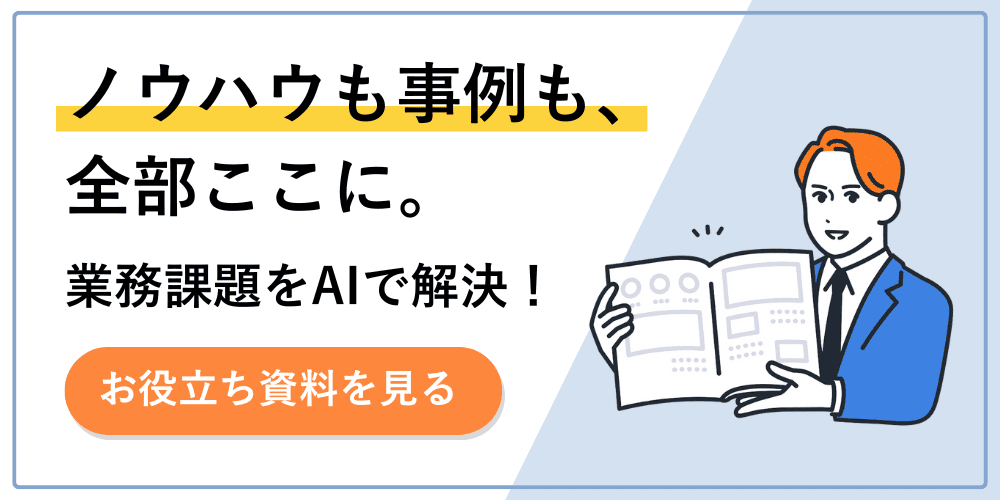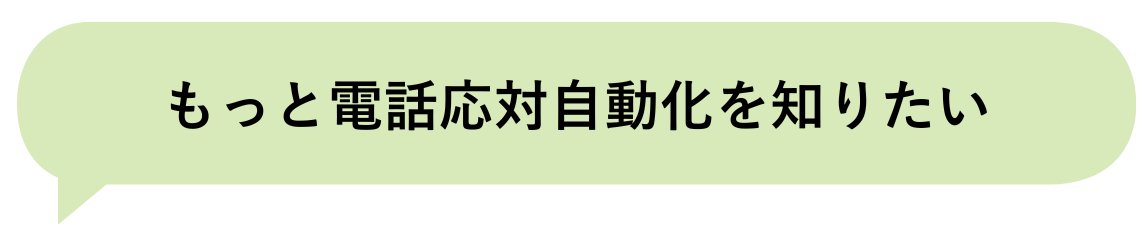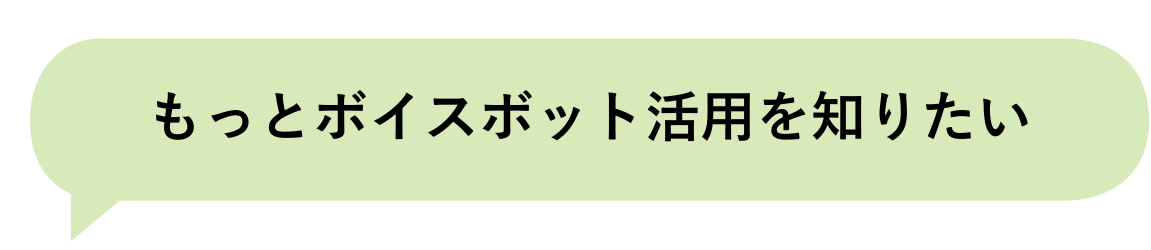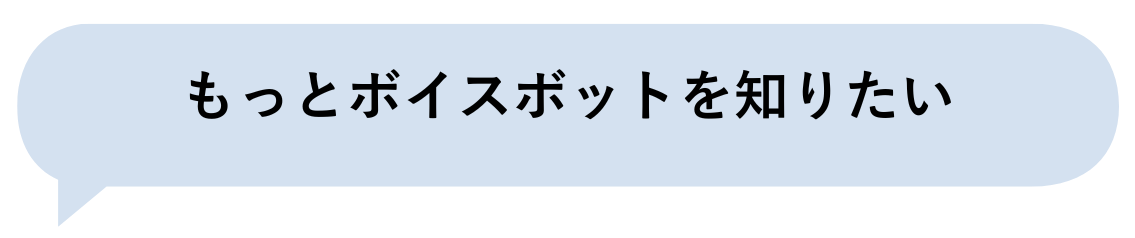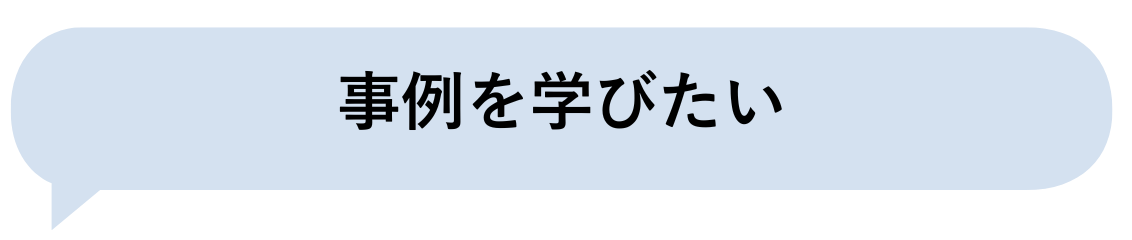コールセンターの課題を解決!効率化や負荷軽減に役立つツール4つを紹介
作成日:2025年10月1日 更新日:2025年10月1日

コールセンターでは、日々多くの顧客から問い合わせがあり、聞き取りから回答までを担っています。
コールセンター市場は年々拡大しているものの、人材不足や応答品質のばらつきなど多くの課題を抱えているのが現状です。
本記事では、コールセンターが抱えている課題を解決する効率化やオペレーターの負荷軽減に役立つツール4つについて紹介します。
コールセンターの課題について漠然とは感じているものの、具体的に課題を把握したいと考えている方やコールセンターの課題解決にAIや自動化ツールをどのように活用すれば良いか知りたい方はぜひ参考にしてください。
コールセンターの主な課題8つ
コールセンター市場は年々拡大しているものの、業務効率化が進んでいない現状があります。コールセンターの主な課題としては、下記の8つがあります。
- 高い離職率と慢性的な人材不足
- 不十分な人材育成
- 応答品質のばらつき
- 多様な問い合わせニーズへの対応
- 顧客の待ち時間
- テレワークの導入
- 繁閑差が大きい
- 顧客の声(VOC)の分析や他部署への共有が不十分
それぞれの課題について詳しくみていきましょう。
高い離職率と慢性的な人材不足
コールセンターの課題として、高い離職率と慢性的な人材不足が挙げられます。
厚生労働省が発表している雇用労働調査によると、2023年には離職率が23.1%と他の業種と比較しても高いです。
特に入社後1年以内に離職するケースが多くみられ、新たに雇用しても長く続かないのが現状です。
このように慢性的な人材不足が続くと、SVやオペレーター1人あたりの負荷が大きくなってしまう点や顧客からの問い合わせに対応しきれないなど業務への影響が大きいといえるでしょう。
不十分な人材育成
人材育成が十分に行われていない点も、コールセンターの課題の一つといえます。
人材育成が充実すると、SVやオペレーターのスキルアップにつながり、業務効率化にも効果があります。
また、育成される社員が今後のキャリアを構築する上でも重要になってくるでしょう。
人材育成が十分に行えない理由としては、人材不足や業務の繁忙などで日々の業務でも手がたりず、人材育成まで時間が費やせない点です。
加えて、オペレーターは電話応対スキルから商品やサービスの知識の習得を、SVはそれらの評価や指導を担いつつ、成果/人員の管理や繁閑調整、トラブル対応、業務改善、ITリテラシやトレンドの学習など、求められる役割が多く、十分なスキルを身につけるまで時間がかかる点も人材育成が進まない理由の一つとして考えられます。また、スキル面だけでなく、顧客との直接的な接点を持つ部門という側面で、応対やその指導に伴うプレッシャーを感じる社員も少なくありません。
応答品質のばらつき
コールセンターでは、オペレーターのスキル差があると応答品質にばらつきがみられます。
オペレーターが少数の場合は応答品質の均一化を図りやすいものの、規模が大きくなるにつれてばらつきが現れやすいです。
応答品質は顧客の満足度にも直結しており、問い合わせに対し誤った対応や顧客が不快に感じる対応があった場合はトラブルやクレームの原因になります。
状況によっては、損害賠償にもつながりかねないケースにまで発展する可能性もあるでしょう。
応答品質を向上させるには、オペレーターのスキル差を解消したり、応答マニュアルを構築したりするなどの対応が必要です。
多様な問い合わせニーズへの対応
近年は顧客からの問い合わせニーズが多様化しており、柔軟な対応が求められています。
コールセンターへの問い合わせ方法は電話以外にも、メール・チャット・Webサイトの問い合わせフォームなどがあります。
素早い回答が求められるだけでなく、普段口頭で説明している内容をテキストで分かりやすく説明しなければなりません。
各チャネルに対応する運用体制の整備とともに、優秀なオペレーターを配置することで多様な問い合わせニーズにも対応できるでしょう。
顧客の待ち時間
顧客の待ち時間が長くなってしまうことも、コールセンターの課題に挙げられます。
問い合わせした顧客にとって電話がつながるまでの時間が長いと、不満やストレスを感じやすいです。
コールセンター白書では、顧客は電話がつながるまでの待ち時間が約20秒までが待てる時間とされています。
また、電話をかけてつながってもオペレーターにつながるまでの待ち時間が長い、もしくは問い合わせ内容に対し保留時間が長いのも顧客にとって不満に感じられるでしょう。
問い合わせ数に対する適正な人員の配置と、問い合わせ内容に迅速に対応できるオペレーターの育成が解決のポイントです。
テレワークの導入
テレワークは、コールセンターのコスト削減やBCP対策、人材不足の解消や働き方の多様化を推進する上で効果的です。
オペレーターの稼働率が激減した新型コロナウイルスの影響で2020年からテレワークの導入が注目されましたが、実際には具体的な導入が上手く進まないケースも多いのが現状です。
進まない理由としては、情報漏洩によるセキュリティリスクが挙げられます。個人情報を多く取り扱う業種のため、情報漏洩が発生した場合は損害賠償が発生し、企業の信用度が大きく低下する恐れがあります。
他にも、オペレーターの勤怠管理・メンタル面での管理や可視化などの点でも考慮すべき点が多く、2024年時点でも運営上の課題と考えているコンタクトセンターは7.3%(※)と、対策の優先順位は低いと考える企業が多いようです。
※2024年コンタクトセンター白書参照
繁閑差が大きい
コールセンターの課題には、繁閑差が大きい点も挙げられます。
時期や時間帯、キャンペーンの実施などでコールセンターの入電数は大きく変化します。
その繁閑差に合わせて、オペレーターの人数・稼働率・人件費などを踏まえてシフトを考えるのがSVをはじめとした管理者の役割です。
ただし、人材不足の観点からメールや入電などのインバウンド業務の対応では、予測を上回る数の処理が発生する事もあるため、キャパシティと人件費を考慮してコントロールするのが難しい時もあります。
顧客の声(VOC)の分析や他部署への共有が不十分
コールセンターではオペレーターが顧客と直接話せるため、お客様が自社サービス利用で感じる不便や疑問などの声(VOC)に触れることができる企業にとって重要な部門です。
しかし、せっかく得たVOCを他部署へと十分に連携できないと、自社のサービスは適切に改善しません。
FAQ・サイト管理などのシステム部門や商品の改善・開発、クロスセル・アップセル、購入前後の顧客へのアプローチなどを担当する営業・マーケティング部門では、VOCを元に移り変わる顧客ニーズを捉えて日々、サービス向上を進める必要があります。
そのため、電話対応部門に集まるVOC連携が不十分だと、改善遅れや誤った改善にもつながりかねません。
コールセンターの課題分析
これらの課題のうち、自社のコールセンターがどの課題を改善すべきかは、定量あるいは定性データを使って判断されます。課題を明確にするには、客観的に数値化する定量分析が効果的です。
課題分析を行う際、成否の判断基準を定めるために活用されるKPIは、コンタクトセンター管理とオペレーター管理とで設定項目が異なります。
ここでは、コールセンターの課題分析に活用される定量/定性分析について、KPIの概要や分析項目の内容について詳しくみていきましょう。
定量分析に活用されるKPIとは
KPIは、重要業績評価指標と呼ばれ、業務の目標達成度合いを評価する指標のことです。
企業が最終目的を達成するため、必要な要素を管理するのに活用されています。
KPIから現在の状況や課題を把握し、改善するといったPDCAを繰り返すことで目標の達成を目指します。
コールセンターでは、電話のつながりやすさや応答品質の高さが顧客満足度に直結することから、KPIを用いて客観的に数値化することは現状を把握するのに効果的です。
コンタクトセンター管理のKPI
コンタクトセンター管理に使われるKPIでは、つながりやすさといった接続品質が測定項目となっています。
具体的な項目内容については、下記の通りです。
- 応答率…全体の総着信に対してオペレーターが対応できた受電件数の割合
- 放棄呼率…全体の総着信に対してオペレーターが対応できなかった受電件数の割合
- サービスレベル…目標時間内に電話に出られた件数の割合
- 平均応答速度…顧客が入電してからオペレーターが電話に出るまでの平均時間
- 話中率…顧客が入電したがオペレーターにつながらず、話し中となってしまった着信率
トランスコスモスが実施した調査によると、コンタクトセンター運営で重要視しているKPIは顧客満足度(CS)のほか、応答率・サービスレベルが挙げられています。
顧客からの入電に対し受話できるだけでなく、いかに早く出られるかという点も求められていることが分かります。
オペレーター管理のKPI
オペレーター管理に使われるKPIとしては、オペレーターの対応の速さといった生産品質が測定項目となっています。
具体的な項目例は、下記の通りです。
- Call Per Hour(CPH)…1人のオペレーターが一定時間内に対応できる処理件数
- 平均処理時間(AHT)…顧客との通話開始から後処理終了までに要した時間の平均値
- 平均通話時間(ATT)…オペレーターが顧客と通話をしている時間の平均値
- 平均後処理時間(ACW)…通話後の後処理(対応履歴入力等)1件あたりにかかる時間の平均値
- 稼働率…オペレーターの労働時間全体から顧客対応にあてられる時間を判断するために用いられる指標
- 占有率…顧客対応にあてられる時間が効率的か判断する為に用いられる指標
- 平均保留時間(AWT)…1件あたりの保留時間の平均値
オペレーターのKPIでは、顧客との応答対応から通話後の処理時間まで一貫してオペレーターの対応速度を計測します。
しかし、通話からこれらの全ての工程をオペレーターが担うとなると業務負荷が大きく、平均処理時間が肥大化してしまいます。
そのため、顧客からの問い合わせ内容を音声認証システムでテキスト化・共有化するなど、オペレーターが行う工程数を少なくする仕組みづくりが重要です。
定性分析によるの課題分析方法
定性データを用いる課題分析の方法としては、コールリーズンやVOCの分析があります。
コールリーズンは、顧客がコールセンターに電話した理由を分析できるヒアリング項目です。
コールリーズンをカテゴライズして傾向を知ることで、トークスクリプトやマニュアルの改善、FAQの見直しなど応対品質の改善が可能になります。
また、顧客の声であるVOCの分析を行うことで、顧客のニーズを把握し、商品やサービスの品質向上や開発に役立てられます。
このように、コールセンターではさまざまな課題分析を行い、現状の把握と改善点をあぶり出し、解決を繰り返すことで目標とする運営を目指すことができます。
コールセンターの効率化・負荷軽減で得られる効果
コールセンターの効率化を推進することでオペレーターの負荷軽減を図れます。
各オペレーターの負荷が軽減されると、下記のような良い効果がみられるようになるでしょう。
- 人材不足の解消
- 離職の抑制
- 応答品質の向上
- 顧客満足度の向上
それぞれの効果がみられる理由について詳しくみていきましょう。
人材不足の解消
コールセンターの業務は習得スキルが多く煩雑であり、オペレーターの負荷が大きいといわれています。
コールセンター業務の効率化が進むと、オペレーターの心理的負荷や身体負荷が軽減されます。
効率化の具体策としては、AIや自動化ツールの導入、人員配置の適正化などです。
初期対応を自動化したり、顧客との応答時間が短縮されたりするとオペレーターの業務負荷が軽減でき、かつ必要人員を削減することも可能です。
よって、慢性的な人材不足の解消にもつながるでしょう。
離職の抑制
コールセンター業務が効率化され、負荷軽減策が実施されることは離職の抑制にも効果があります。
人材不足による業務の繁忙や多様な問い合わせへの対応は、オペレーターにとって大きな負荷となっています。
コールセンター業務の効率化により、オペレーターの負荷を軽減すると、業務負荷を原因とするオペレーターの離職に歯止めをかけられるでしょう。
離職率が低下すると、安定した人材確保につながります。
応答品質の向上
コールセンター業務の効率化は、応答品質の向上にも良い影響があります。
オペレーター各人にレベル差があると応答品質にばらつきが現れやすいですが、AI・自動化すると応答品質が均一化されます。
また、人材育成に携わる時間も生み出せるので、オペレーターのスキルアップにも効果があるといえるでしょう。
各オペレーターがスキルアップすると、オペレーターのスキル差がなくなり、応答品質が向上します。
顧客満足度(CS)の向上
コールセンター業務の効率化・オペレーターの負荷軽減が進むと、顧客満足度(CS)が向上します。
顧客にとってはコールセンターに問い合わせするとすぐにつながり、不明点が解消される状態を求めています。
そのため、コールセンター業務の効率化により電話がつながりやすくなり、問い合わせ内容に対応できるオペレーターにつながる仕組みがあると、スムーズな対応が可能です。
顧客と直接やり取りするコールセンター業務は効率化することで、顧客満足度の向上により最終的には企業の生産性や売り上げのアップにも効果があるといっても過言ではありません。
コールセンターの効率化・自動化に活用されているツール4つ
コールセンターの課題解決方法の一つとして、AI・自動化ツールの活用があります。
コールセンターで活用できるAI・自動化ツールはさまざまありますが、具体的にはどのように効率化されるのでしょうか。
ここでは、コールセンターの課題解決に直結するツール4つについて詳しくみていきましょう。
ボイスボット
ボイスボットとは、AI(人工知能)を活用して音声認識や自然言語処理などの技術によって、電話での自動応答を行うシステムのことです。
自然な会話を行いながら顧客の問い合わせに対し、回答までの対応が可能なため、人員削減やコールセンター業務の効率化に効果的なAI・自動化ツールです。
顧客の問い合わせ窓口や商品・サービスの申込などの電話対応に活用されるケースがよくみられます。
チャットボット
チャットボットとは、チャットとロボットを組み合わせたものでAIや自然言語処理の技術を活用してテキストでの自動応答を行うシステムのことです。
Webサイトや問い合わせチャットなどに寄せられる顧客からの問い合わせに適切な回答を生成し、テキスト化して回答します。
24時間対応の問い合わせ窓口設置が必要な場合や、問い合わせチャネルの多様化に対応する場合にチャットボットが活用されるケースがよくみられます。
音声認証システム
音声認証システムとは、顧客の会話をAIが分析し、テキスト化するシステムです。
コールセンターに問い合わせてきた顧客とオペレーターとの会話をテキスト化することで正確に通話内容を把握でき、素早くかつ適切な回答を顧客に行えます。
また、音声認証システムは応答品質の向上や業務の短縮化だけでなく、オペレーターのフィードバックにも効果的です。
CRM
CRMとは、顧客情報やこれまでのやり取りなどの情報を一元管理するシステムのことです。
コールセンターでのCRM活用法としては、電話番号と連動させることで入電とともにこれまでに購入した商品やサービスの内容やこれまでの対応履歴を一目で確認できます。
また、顧客情報の管理だけでなく、蓄積された情報をデータ分析し、営業やマーケティングへの活用も可能です。
CRMを導入すると、どのオペレーターが対応しても顧客の情報が共有化されているため、応答時間の短縮や応答品質の向上に一役を担うことが可能です。
コールセンターの課題解決にボイスボットを導入するメリット・デメリット
コールセンターの課題解決で活用するAI・自動化ツールの中でも、近年ボイスボットを導入する企業が増えています。
ボイスボットとはそもそもどのようなツールなのでしょうか。
ここでは、ボイスボットの概要と導入するメリット・デメリットについて詳しくみていきましょう。
ボイスボットの概要
ボイスボットは、AIと自然言語処理の技術を活用して自然な会話を行いながら顧客の会話内容をテキスト化します。
そして、顧客の問い合わせ内容を解析し、内容に適した回答を生成してテキスト化し、顧客へ回答を行います。
顧客にとってはオペレーターと会話している時と同じように、ボイスボットとの会話の中で不明点を伝えると適切な回答を得ることが可能です。
ボイスボットのメリット
ボイスボットのメリットとしては、下記のような点が挙げられます。
- オペレーターの負荷軽減
- 離職率の低下
- 人件費削減
- 顧客ニーズの分析
- 応答品質の向上
- 顧客満足度の向上
ボイスボットの導入によりコールセンター業務の一部を自動化できるので、オペレーター一人あたりの業務量が軽減できます。
そのため、オペレーターの負荷軽減につながり離職対策としても効果があるといえるでしょう。
また、ボイスボットによる自動化で応答品質が均一化されるため、顧客満足度の向上にもつながります。
ボイスボットと顧客との通話内容は情報として蓄積され、顧客ニーズの分析や他部署への連携にも役立てられます。
最終的には企業の商品・サービスに対する顧客の声が反映され、収益の向上にもつながるでしょう。
ボイスボットのデメリット
ボイスボットのデメリットとしては、下記のような点が挙げられます。
- 音声認証の精度が低いと正確に内容把握できない
- 複雑な問い合わせへの対応が難しい
- 騒音が入ると認証しにくい
- 学習データをある程度準備し、定期的にチューニングが必要
ボイスボットでは顧客の音声認証が重要になりますが、精度が低いと正確に通話内容を認証できず回答がうまく生成できないことがあります。
また、複雑な問い合わせが多い場合はボイスボットでは対応が困難になります。
その場合は、一次対応はボイスボットで自動化し、詳細についてはオペレーターが対応するなどの役割分担が必要です。
加えて、ボイスボット導入前にあらかじめある程度の学習データを準備して学習させるとともに、導入後も定期的にチューニングをして精度を高める必要があります。
ボイスボット導入の活用例
ボイスボット導入の活用例としては、代表電話の一次対応・注文あふれ呼対策・手続きの受付対応などがあります。
ボイスボットは代表電話への問い合わせや担当者への取り次ぎも自然な会話でスムーズに行えるうえ、発信者の電話番号や受話時の通話の記録も残すことが可能です。
また、通販やECでよくみられる広告後の注文あふれ呼にも取りこぼしなく対応できるので、受注率のアップが期待できます。
そして、手続きの受付対応は定型の会話で進められることも多いことから、ボイスボットを活用することで目標KPIを早期達成できるケースも多くみられています。
コールセンターの課題解決ならボイスボットで効率化しよう
本記事では、コールセンターが抱える課題について分析方法や解決方法、効率化・負荷軽減で得られる効果を紹介しました。
コールセンターには人材不足や応答品質など多くの課題を抱えていますが、人件費の引き上げや教育体制の強化など、社内リソースのみで対処するのが難しいケースが多くあります。その切り札として、AI・自動化ツール導入も手段の一つです。
直近注目されているボイスボットの導入は、人材不足や応答品質の平準化のほか、コスト削減や業務の効率化、オペレーターの負荷軽減などに効果があります。
AIボイスボット「commubo(コミュボ)」は自然な会話で対応できるだけでなく、既存の電話システムやCRMシステムとも膨大な開発コストなくスムーズに連携でき、カスタマイズも自社で簡単にできておすすめです。

commuboラボとは?
AIを活用した業務効率化×顧客満足向上を研究するメディアです。
今まで400社以上に電話応対自動化ソリューションを提供してきたソフトフロントが、自動化の考え方や、ボイスボット活用のコツ、お客様の活用事例、AI活用のトレンドなどをご紹介し、企業の生産性向上だけでなく、その先のお客様の顧客体験(CX)向上に役立つ情報を提供していきます。